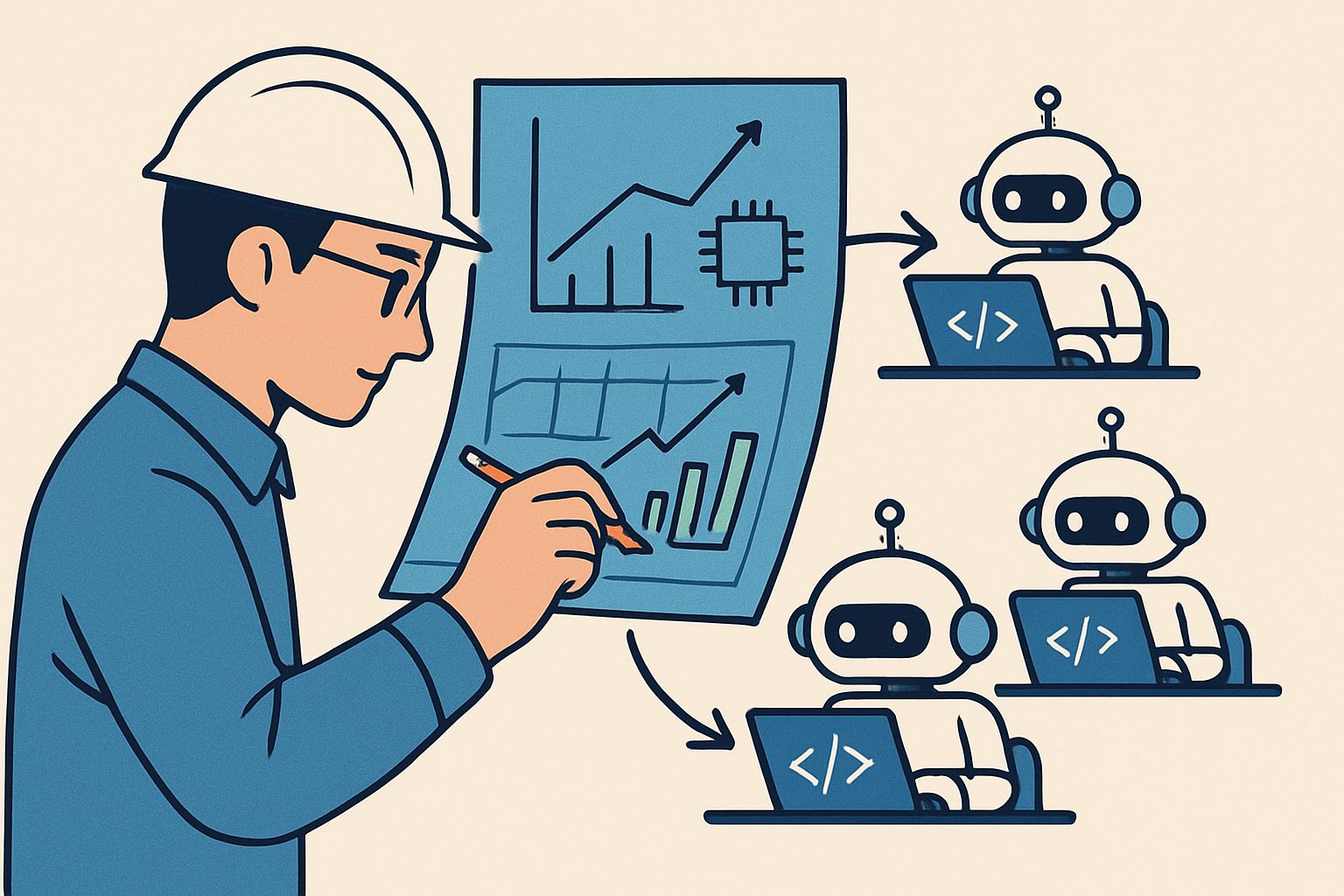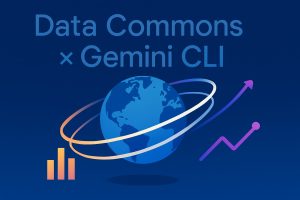はじめに
本稿では、GitHubの公式ブログで公開された記事「How we accelerated Secret Protection engineering with Copilot」を基に、AIコーディングエージェントであるGitHub Copilotを活用して、セキュリティ機能の開発プロセスを大幅に高速化した具体的な事例を解説します。
参考記事
- タイトル: How we accelerated Secret Protection engineering with Copilot
- 発行元: The GitHub Blog
- 発行日: 2025年8月28日
- URL: https://github.blog/ai-and-ml/github-copilot/how-we-accelerated-secret-protection-engineering-with-copilot/
要点
- GitHubは、ソースコードに漏洩した認証情報(シークレット)の有効性を自動で検証する機能のカバレッジ拡大に、AIコーディングエージェントを活用した。
- 人間が「調査」や「レビュー」といった判断を要する作業を担当し、AIが「コーディング」や「リリース設定」といった定型的な作業を担当するという、明確な役割分担を確立した。
- このアプローチにより、従来は数ヶ月を要していた作業をわずか数週間に短縮し、検証対象のトークン種類を32から一気に120近くまで、約90種類も追加することに成功した。
- 本事例は、フレームワーク化された反復的な開発タスクにおいて、AIエージェントが人間のエンジニアの生産性を飛躍的に向上させる強力なパートナーとなり得ることを示すものである。
詳細解説
背景:ソースコードへの「シークレット」漏洩という深刻な問題
開発者が最も恐れるミスの一つに、APIキーやパスワード、証明書といった「シークレット」と呼ばれる機密情報を、誤ってソースコードに含んだまま公開リポジトリなどにコミットしてしまうことがあります。これが悪用されると、不正アクセスや情報漏洩、金銭的な被害に繋がる可能性があり、非常に深刻な問題です。
GitHubは、この問題に対処するために「Secret Protection」という機能を提供しています。これは、リポジトリ内のコードをスキャンし、漏洩した可能性のあるシークレットを検知して開発者に警告する仕組みです。
この機能の中でも特に重要なのが「有効性チェック(Validity checks)」です。検知されたシークレットが、実際にアクセス可能な「有効な(アクティブな)キー」なのか、それとも既に無効化されているキーなのかを、各サービスプロバイダーのAPIに問い合わせて自動で確認します。これにより、開発者は本当に対処が必要なアラートに集中できるようになります。
課題:人手では限界のあるカバレッジ拡大
GitHubチームは、当初AWSやGCP、Slackなど、よく利用される主要なサービスのトークンに対する有効性チェックを実装しました。しかし、世の中には無数のサービスとトークン形式が存在します。より多くのサービスに対応するためには、サービスごとに検証ロジック(Validator)を追加開発し続ける必要がありました。
この追加開発は、以下のような定型的ながらも手間のかかるワークフローを伴います。
- 調査 (Research): 新しいトークンを安全に検証するための、最適なAPIエンドポイント(例えば、ユーザー情報を取得する /me のようなエンドポイント)をドキュメントなどから探し出す。
- コーディング (Code): 調査結果に基づき、検証ロジックを実装する。
- ダークシップ (Darkship): 新しい検証ロジックを本番環境で動かし、データベースに結果を書き込まずに動作を観察する。APIの仕様がドキュメントと微妙に違う場合などに備え、エラーを修正する期間。
- リリース (Release): 問題がないことを確認し、ダークシップ設定を解除して本格的に機能を有効化する。
このプロセスは、一つ一つは複雑ではないものの、対応すべきトークンの種類が増えるにつれて、エンジニアの時間を大きく消費し、開発のボトルネックとなっていました。
解決策:AIとの協業という新しいアプローチ
そこでチームが着目したのが、AIコーディングエージェントであるGitHub Copilotの活用です。彼らは、前述のワークフローを分析し、人間がやるべき作業とAIに任せられる作業を切り分けました。
- 人間が担当する領域(判断と思考が必要):
- 調査 (ステップ1): どのAPIエンドポイントが最も影響範囲が少なく安全かを判断するには、経験に基づいたエンジニアの知見が必要でした。Copilotにこの作業を任せたところ、必ずしも最適なエンドポイントを見つけられないことが分かりました。
- レビューとデプロイ: Copilotが生成したコードが本当に正しいか、セキュリティ上の問題はないかを確認し、最終的にデプロイするのは人間のエンジニアの重要な責務です。
- AI (Copilot) が担当する領域(定型的で反復的):
- コーディング (ステップ2): 人間による調査結果(使用するAPIエンドポイント、期待される応答など)を詳細な指示書(プロンプト)として渡せば、検証ロジックのコード生成は自動化可能でした。
- リリース (ステップ4): ダークシップを解除するための設定変更も、非常に単純な作業であるため、Copilotに依頼することで自動化できました。
AIとの具体的な連携プロセス
この役割分担に基づき、チームは以下のような洗練されたワークフローを構築しました。
- エンジニアが調査を終えると、その結果(トークン名、プロバイダー名、APIドキュメントURL、エンドポイントURLなど)をGitHub Actionsのワークフロー実行画面に入力します。
- ワークフローが起動し、入力された情報を基に、Copilotにタスクを依頼するための詳細なIssueを自動で生成します。 このIssueが、Copilotにとっての高品質なプロンプトとなります。
- CopilotがそのIssueを読み込み、検証ロジックの実装を含んだプルリクエストを自動で作成します。
- エンジニアは、生成されたコードをレビューします。修正が必要な場合は、プルリクエストにコメントを付けるだけで、Copilotに修正を再依頼できます。
- コードが承認されると、エンジニアがデプロイし、ダークシップ期間に入ります。
- ダークシップ期間が終了したら、再度Copilotに依頼して、機能を有効化するプルリクエストを作成・マージします。
このプロセスは、Copilotを単なるコード補完ツールとしてではなく、自律的にタスクをこなすチームの一員として扱っている点が重要です。
成果と学び
このAIとの協業体制を導入した結果、その効果は絶大なものでした。
- 導入前: 数ヶ月かけて32種類のトークンに対応。
- 導入後: わずか数週間で、新たに約90種類のトークンに対応。
特筆すべきは、このタスクを主導したのがエンジニアリングインターンであった点です。彼らがCopilotを指揮することで、本来であれば多くのシニアエンジニアのリソースを必要とするタスクを、驚異的なスピードで並列処理することができました。これはCopilotが文字通り「戦力増強装置(Force Multiplier)」として機能したことを示しています。
この取り組みから得られた重要な学びは以下の通りです。
- 自動化は反復可能なプロセスでこそ輝く: 明確に定義されたステップを持つワークフローは、AIによる自動化の絶好の候補です。
- AIをチームメンバーとして扱う: AIが生成したコードも、人間が書いたコードと同様に、慎重なレビュー、テスト、フィードバックが必要です。
- プロンプトの質が結果を左右する: 詳細で具体例が豊富なプロンプトを用意することが、高品質なアウトプットを引き出す鍵となります。
- 並列化という強み: この仕組みにより、複数のトークンに対する追加作業を同時に進行させることが可能になり、開発のボトルネックが解消されました。
まとめ
本稿で紹介したGitHubの事例は、AIコーディングエージェントが開発の現場でいかに強力なツールとなり得るかを示す、非常に興味深いものです。重要なのは、AIに全ての作業を任せるのではなく、定型的・反復的なタスクをAIに委譲し、人間はより創造的で高度な判断が求められる作業に集中するという、戦略的な役割分担です。
AIは人間の仕事を奪うのではなく、むしろ人間を面倒な作業から解放し、生産性を飛躍的に向上させるためのパートナーとなり得ます。日本の開発チームにおいても、自分たちのワークフローの中に潜む「反復可能なタスク」を見つけ出し、AIとの協業を検討することで、開発プロセスを大きく変革できる可能性を秘めていると言えるでしょう。