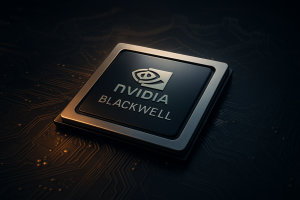はじめに
本稿では、Nvidiaの中国市場向け新型AIチップに関するニュースについて、ロイターの2025年5月24日付記事「Exclusive: Nvidia to launch cheaper Blackwell AI chip for China after US export curbs, sources say」をもとに解説します。
引用元記事
- タイトル: Exclusive: Nvidia to launch cheaper Blackwell AI chip for China after US export curbs, sources say
- 発行元: Reuters
- 発行日: 2025年5月24日
- URL: https://www.reuters.com/world/china/nvidia-launch-cheaper-blackwell-ai-chip-china-after-us-export-curbs-sources-say-2025-05-24/

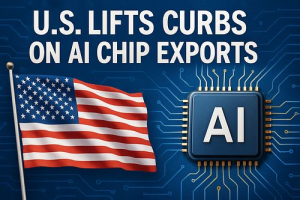
要点
- Nvidiaは、米国の輸出規制に対応するため、中国市場向けに性能を調整した新しいAIチップを開発中である。
- この新チップは、最新のBlackwellアーキテクチャをベースとしつつ、従来のH20モデルよりも低価格で提供される見込みである。
- 具体的には、価格帯は6,500ドルから8,000ドルとされ、H20の10,000ドルから12,000ドルよりも大幅に安価になる。
- 性能調整の一環として、先端パッケージング技術CoWoSを使用せず、メモリもGDDR7を採用するなど、製造コストと性能のバランスを取る設計となる。
- この動きは、Nvidiaにとって依然として重要な中国市場でのシェアを維持し、Huaweiなどの競合に対抗するための戦略である。
- 米国政府による輸出規制は、特にGPUのメモリ帯域幅に新たな制限を課しており、Nvidiaはこの規制の範囲内で最大限の性能を発揮するチップを設計する必要がある。
詳細解説
米国による輸出規制とその背景
近年、米国政府は国家安全保障上の懸念から、中国への先端半導体技術の輸出規制を強化しています。特にAI開発に不可欠な高性能GPU(Graphics Processing Unit)は、その主要なターゲットとなっています。NvidiaはAI向けGPU市場で圧倒的なシェアを誇りますが、この規制によって中国への最先端チップの輸出が制限されてきました。
今回の報道にある新しいチップ開発は、こうした規制環境下でNvidiaが中国市場へのアクセスを維持するための新たな試みと言えます。中国はNvidiaにとって依然として巨大な市場であり、2024年度の売上の13%を占めていました。しかし、規制の影響で同社の中国での市場シェアは、2022年以前の95%から現在は50%まで低下していると報じられています。
新型チップの技術的特徴:Blackwellアーキテクチャと性能調整
報道によると、Nvidiaが開発中の中国向け新チップは、同社の最新世代AIプロセッサであるBlackwellアーキテクチャをベースにしています。しかし、米国の輸出規制をクリアするために、いくつかの重要な技術的変更が加えられる見込みです。
- 価格と性能のバランス:
- 新チップの予想価格は6,500ドルから8,000ドルとされており、これは中国向けに既に投入されていたH20モデル(10,000ドル~12,000ドル)よりも大幅に安価です。この価格設定は、性能を抑えることと、製造コストを削減することで実現されると考えられます。
- メモリ技術の変更:
- 新チップは、より高度なHBM(High Bandwidth Memory)の代わりに、従来のGDDR7メモリを採用すると報じられています。HBMは非常に高速なデータ転送が可能ですが、コストが高く、また輸出規制の対象となりやすい技術です。GDDR7はHBMに比べると帯域幅は劣りますが、コストを抑えつつ一定の性能を確保できる選択肢となります。
- 最新の輸出規制では、GPUのメモリ帯域幅に新たな上限(Jefferiesの推計では1.7~1.8テラバイト/秒)が設けられています。H20が4テラバイト/秒の帯域幅を持っていたのに対し、新チップはGDDR7メモリ技術を用いて、この規制上限に近い約1.7テラバイト/秒のメモリ帯域幅を実現するとGF Securitiesは予測しています。メモリ帯域幅は、AIワークロードのように大量のデータを処理する際に非常に重要な指標です。
- パッケージング技術の簡素化:
- 台湾のTSMCが提供する高度なCoWoS(Chip-on-Wafer-on-Substrate)パッケージング技術を使用しないとされています。CoWoSは、複数のチップを高密度に集積することで性能を向上させる技術ですが、これもまたコスト増の要因であり、供給も逼迫しやすい技術です。この技術を回避することで、製造コストの削減とサプライチェーンの安定化を図る狙いがあると考えられます。
- ベースとなるGPU:
- 記事によれば、この新チップはサーバークラスのグラフィックプロセッサである「RTX Pro 6000D」をベースにしているとのことです。
これらの技術的変更は、Nvidiaが米国の輸出規制の枠内で、中国市場の顧客にとって魅力的な価格と性能のバランスを持つ製品を提供しようとする戦略的な判断を反映しています。
Nvidiaの中国市場戦略と競合
NvidiaのCEOであるジェンスン・フアン氏は、米国の輸出規制が続けば、より多くの中国の顧客がHuaweiのような国内企業のチップを購入するようになるだろうと警告しています。実際に、HuaweiはAscend 910BといったAIチップを開発し、Nvidiaの強力な競合相手として台頭しています。
今回報じられた新チップは、Nvidiaにとって3度目の中国市場向けカスタマイズ製品となります。以前にも規制に対応するためにH100やA100といった高性能チップのダウングレード版(H800、A800)を開発しましたが、これらも後の規制強化で使用できなくなりました。直近ではH20というモデルを投入しましたが、これも4月に事実上禁止されたと報じられています。フアンCEOは、H20が採用していたHopperアーキテクチャでは、現行の輸出規制下でこれ以上の変更は困難であると述べており、これがBlackwellアーキテクチャをベースとした新チップ開発の背景にあると考えられます。
Nvidiaは、この新チップ(GF Securitiesは「6000D」または「B40」という名称になる可能性を指摘)に加えて、早ければ9月にも生産開始予定の別のBlackwellアーキテクチャベースの中国向けチップも開発中であると報じられており、中国市場へのコミットメントの強さがうかがえます。
日本への影響と今後の展望
今回のNvidiaの動きは、直接的には中国市場向けの対応ですが、間接的に日本を含むグローバルなAIチップ市場にも影響を与える可能性があります。
- グローバルな供給バランスの変化: 特定市場向けの製品開発は、Nvidia全体の生産リソース配分に影響を与える可能性があります。ただし、今回報じられているチップは、CoWoSのような先端パッケージング技術を使用しないため、最先端チップの供給逼迫を緩和する方向に働くかもしれません。
- 技術開発の方向性: 輸出規制という制約の中で、いかに性能を最適化するかというNvidiaの取り組みは、今後のチップ設計における新たな視点を提供するかもしれません。コスト効率と性能のバランスを追求する動きは、より広範な市場セグメント向けの製品開発にも影響を与える可能性があります。
- 地政学リスクの顕在化: 米中間の技術覇権争いは、半導体産業全体に大きな不確実性をもたらしています。日本企業も、こうした地政学リスクを考慮したサプライチェーン戦略や技術開発戦略を策定する必要性が高まっています。
Nvidiaの広報担当者は、「新たな製品設計を決定し、米国政府の承認を得るまでは、事実上、中国の500億ドル規模のデータセンター市場から締め出されている」とコメントしており、新チップの投入にはまだ不確定要素も残されています。今後の米国政府の動向や、Nvidiaの正式な発表が注目されます。
まとめ
本稿では、ロイターの報道に基づき、Nvidiaが米国の輸出規制に対応するために開発中とされる中国市場向けの新しいAIチップについて解説しました。この動きは、米中間の技術摩擦という大きな文脈の中で、Nvidiaが巨大な中国市場でのビジネスを継続するための重要な戦略です。
新チップは、最新のBlackwellアーキテクチャをベースとしつつも、メモリ技術の変更や先端パッケージング技術の不使用といった性能調整とコスト削減が図られています。これは、米国の輸出規制、特にメモリ帯域幅の制限を遵守しつつ、中国の顧客にとって魅力的な製品を提供するための苦心の結果と言えるでしょう。
Nvidiaにとって中国市場の重要性は依然として高く、Huaweiなどの現地競合企業との競争も激化しています。このような状況下で投入される新チップが、Nvidiaの中国における市場シェア回復にどの程度貢献するのか、そしてグローバルなAIチップ市場にどのような影響を与えるのか、今後の動向を注視していく必要があります。日本にとっても、このニュースは先端技術を巡る国際情勢の複雑さと、それに対応する企業の戦略を理解する上で示唆に富むものと言えるでしょう。