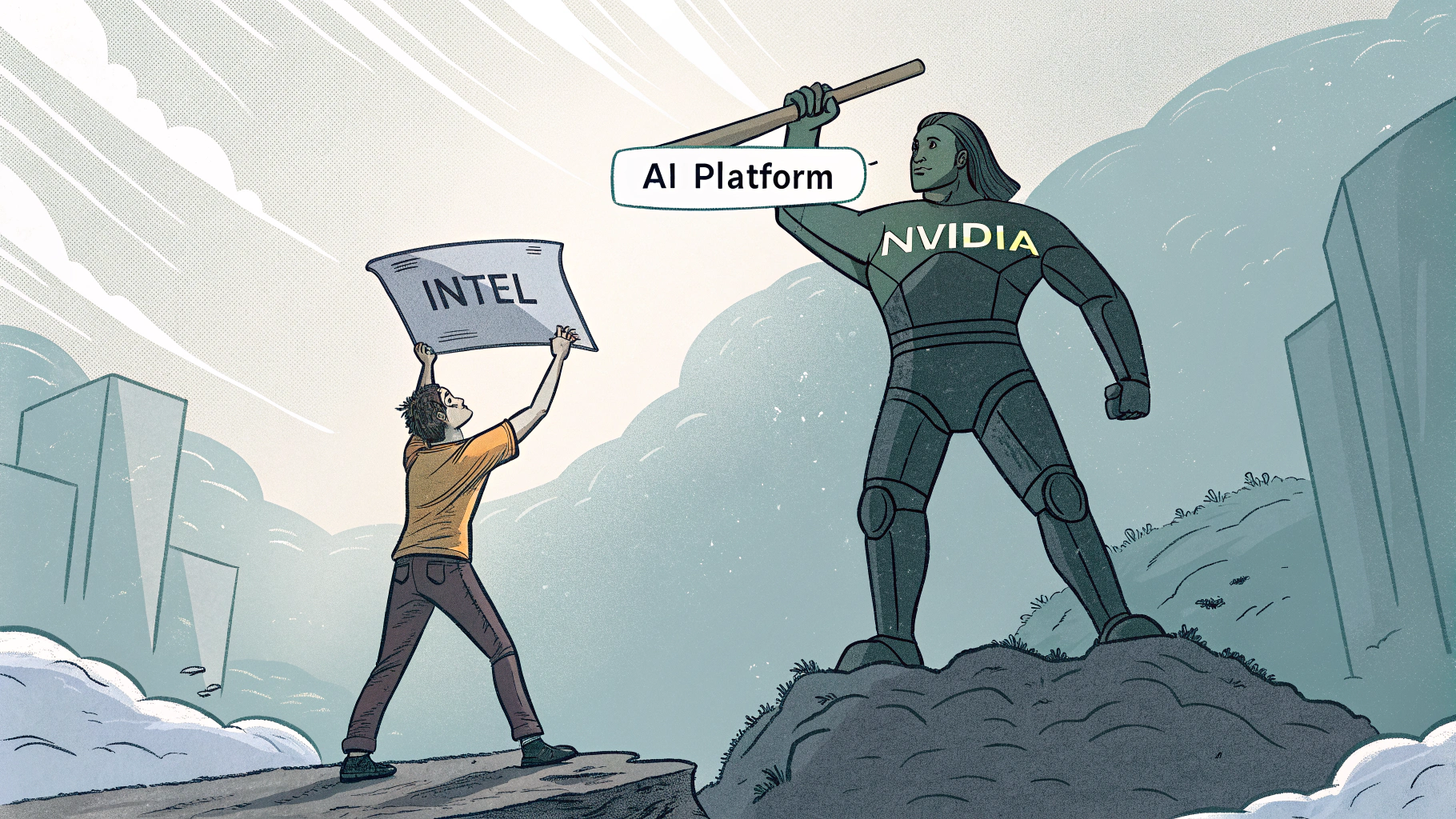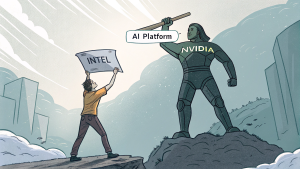はじめに
近年、AI(人工知能)技術は目覚ましい発展を遂げ、私たちの生活やビジネスに大きな変化をもたらしています。このAI技術の根幹を支えているのが、高性能な「AIチップ」です。現在、この市場ではNVIDIAが圧倒的なシェアを誇っていますが、長年CPU市場をリードしてきたインテルが、この状況を変えようと新たな戦略を打ち出しました。本稿では、ロイター通信の記事を元に、インテルが過去の戦略を転換し、どのようにしてNVIDIAに挑戦しようとしているのか、その背景や具体的な計画、そして立ちはだかる課題について、分かりやすく解説します。
引用元記事
- タイトル: After years of failed AI deals, Intel plans homegrown challenge to Nvidia
- 発行元: Reuters
- 発行日: 2025年4月25日
- URL: https://www.reuters.com/business/after-years-failed-ai-deals-intel-plans-homegrown-challenge-nvidia-2025-04-25/
・本稿中の画像に関しては特に明示がない場合、引用元記事より引用しております。
・記載されている情報は、投稿日までに確認された内容となります。正確な情報に関しては、各種公式HPを参照するようお願い致します。
・内容に関してはあくまで執筆者の認識であり、誤っている場合があります。引用元記事を確認するようお願い致します。
要点
- インテルは過去10年間、AIチップ市場でNVIDIAに対抗できず、大きな過ちを犯したと認識しています。
- 新CEOのLip-Bu Tan氏は、これまでの買収頼みの戦略から転換し、自社開発(homegrown)を中心としたAI戦略を進める方針を示しました。
- 既存製品の見直しや、ロボティクス、AIエージェントといった新たなAIトレンドに対応できる製品開発を目指します。
- NVIDIAがチップだけでなくシステム全体(ケーブル、ソフトウェア含む)を提供するように、インテルも同様のアプローチ(holistic approach)を目指し、顧客にとって選択されるプラットフォームとなることを目標としています。
- ただし、財務状況の改善を優先するため、当面は大規模な買収は控える方針です。
- NVIDIAの圧倒的な市場支配力や、AmazonやGoogleなど大手クラウド企業による自社製AIチップ開発の動きもあり、インテルの挑戦は容易ではないとの見方もあります。
詳細解説
AIの計算処理には、一般的なコンピュータに使われるCPU(中央演算処理装置)よりも、特定の計算を並行して大量にこなせるGPU(画像処理装置)や、さらに特化したAIチップが適しています。NVIDIAはこのGPU技術をAI分野に応用することで市場を席巻しました。
一方、CPUの巨人であるインテルは、このAIチップの波に乗り遅れてきました。記事によると、インテルはこの10年間、AI分野でのNVIDIAの優位性を覆せなかったことを大きな失敗と捉えています。これまでインテルは、Movidius、Mobileye、Nervana、Habana LabsといったAI関連のスタートアップ企業を次々と買収することで、AI市場への食い込みを図ってきました。しかし、自動運転分野でMobileyeが一定の地位を保ったものの、他の買収はNVIDIAに対抗する上で十分な成果を上げられませんでした。
そこで、新たにCEOに就任したLip-Bu Tan氏は、方針転換を表明しました。これまでの買収頼みではなく、インテル社内での開発(homegrown)に重点を置くというのです。具体的には、既存の製品ラインナップを見直し、ロボット工学や、ユーザーの代わりにタスクを実行する「AIエージェント」のような新しいAIの応用分野に向けて最適化していく計画です。
さらに重要なのは、インテルが目指すアプローチの変化です。現在のAI市場のリーダーであるNVIDIAは、単にチップを売るだけでなく、チップ、ケーブル、さらにはソフトウェア開発環境(コンパイラ)まで含めたデータセンター全体のソリューションを提供しています。Tan氏は、インテルもこれと同様に、ハードウェアからソフトウェアまでを統合した「プラットフォーム」として提供し、顧客から「選ばれる存在」になることを目指すと述べています。これは、単なる部品メーカーから、AIソリューション全体の提供者へと脱皮しようとする野心的な試みと言えます。
しかし、この戦略転換には課題も山積しています。まず、CFO(最高財務責任者)のDavid Zinsner氏が述べているように、インテルは現在、財務体質の改善を優先しており、当面は大規模な企業買収を行わない方針です。つまり、新たなAI戦略の実現は、主に自社のリソースに頼らざるを得ません。
また、市場環境もインテルにとって厳しいものがあります。NVIDIAの市場での地位は盤石であり、さらにAmazonやGoogleといった巨大クラウドコンピューティング企業も、自社サービスに最適化した独自のAIチップ開発を進めています。インテルが割って入る余地は限られている、と指摘するアナリストもいます。
インテルが具体的に注力する分野としては、AIアプリケーションを実行するためのチップやシステム、そしてスマートフォンやセンサーなど、クラウドではなく現場に近い場所(エッジ)でAI処理を行う「エッジデバイス」が挙げられています。これらの分野は将来性があるものの、その成長の規模や速度はまだ不透明である、という慎重な見方もあります。
アナリストのBob O’Donnell氏は、「インテルが適切なソフトウェアサポートを構築し、新しいチップの導入を容易にできればチャンスはあるが、それは大きな賭けだ」とコメントしており、技術力だけでなく、開発者やユーザーが使いやすい環境を整えられるかが成功の鍵となりそうです。
まとめ
本稿では、インテルがAIチップ市場でNVIDIAに対抗するため、これまでの買収中心戦略から自社開発中心へと舵を切った新たな戦略について解説しました。NVIDIAが築き上げたエコシステムや、大手クラウド企業の動向など、インテルを取り巻く環境は依然として厳しいものがあります。しかし、インテルが持つ技術力と、「プラットフォーム」としてAIソリューション全体を提供しようという「holistic approach」が成功すれば、AIチップ市場の勢力図が変化する可能性も秘めています。インテルがこの「容易ではない挑戦(not a quick fix)」にどのように取り組み、成果を出していくのか、今後の動向が注目されます。