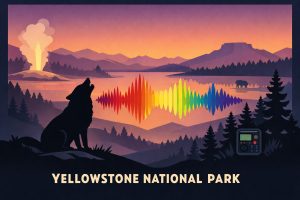はじめに
本稿では、Googleが2025年9月24日に報じた、同社の動画生成モデル「Veo」を活用した新たなアートプロジェクトについて解説します。このプロジェクトは、Google Arts & Cultureと京都、福田美術館の協業によるもので、静止画である美術コレクションをアニメーション化する「Moving Paintings(動く絵画)」という試みです。
参考記事
- タイトル:How Veo is helping the Fukuda Art Museum create “Moving Paintings”
- 発行元:Google
- 発行日:2025年9月24日
- URL:https://blog.google/outreach-initiatives/arts-culture/how-veo-is-helping-the-fukuda-art-museum-create-moving-paintings/
- プロジェクトページ:https://artsandculture.google.com/experiment/vwGt6nKBuhLotg
要点
- Google Arts & Cultureは、京都の福田美術館と協業し、所蔵作品をアニメーション化する「Moving Paintings」プロジェクトを開始した。
- このプロジェクトには、Googleの動画生成モデル「Veo」が活用されている。
- Veoは、一枚の静止画から、時間的に一貫性のある自然な動きを持つ動画を生成する能力を持つ。
- 活用方法には、作品の物語性を引き出す「アニメーションモード」と、作品が描かれたであろう現実世界を再現する「フォトリアリスティックモード」の2種類が存在する。
- この取り組みは、アートの新しい鑑賞方法を提供し、文化遺産の保存と活用の可能性を広げるものである。
詳細解説
アート鑑賞の新たな挑戦:「静止画」の先へ
一枚の絵画や歴史的な写真には、その瞬間の光景だけでなく、フレームの外に広がる物語の可能性が秘められています。しかし、これらをデジタルで紹介する際、静止画という形式の制約を超えることは、技術的にも学術的にも大きな課題でした。
この課題に対し、Google Arts & Cultureは、福田美術館との連携を通じて一つの解決策を提示しました。それが、Googleの動画生成モデル「Veo」を用いて、静的なアート作品に生命を吹き込む「Moving Paintings」プロジェクトです。
Veoが実現する2つの動作モード
Veoは、一枚の画像やテキストによる指示(プロンプト)から、高品質で現実に近い動画を生成するために開発されたGoogleによるAIモデルです。
Google Arts & Cultureは、Veoを活用するにあたり、異なる目的を持つ2つの動作モードを開発しました。
1. アニメーションモード:作品に秘められた物語を可視化する
このモードは、学芸員など専門家の知見に基づいて、作品内の物語性を引き出すことを目的としています。専門家が絵の中に暗示されている「降りしきる雨」や「通り過ぎる旅人」、「はためく旗」といった要素を具体的な動きのベクトルとして定義します。
Veoは、この指示を基に、連続的で高精細な映像を生成します。これにより、画家の筆がキャンバスを離れた「後」の瞬間が可視化され、作品に込められた物語がより明確な視覚体験として鑑賞者に届けられます。
2. フォトリアリスティックモード:作品の「源泉」を想像する
このモードは、「この絵が描かれた場所は、実際にはどのような光景だったのか」という問いに答えることを目指します。静止画を「視覚的な種(visual seed)」として用い、その絵の源泉となったであろう写実的な世界をシミュレートした高忠実度の動画を生成します。
これは、一枚の画像を手がかりに、時間的に安定した環境をコンピュータビジョンが予測するプロセスです。芸術的な解釈が加えられる前の、ありのままの現実世界をデジタルウィンドウからのぞき込むような体験を提供します。
プロジェクトの意義と今後の展望
この「Moving Paintings」プロジェクトは、デジタルアーカイブを分析可能な動的資産へと拡張することで、文化遺産の保存と視覚的なストーリーテリングの両面に新たな道を切り開く可能性があるものです。アートへのアクセスを容易にし、より多くの人々が文化に触れる機会を創出することが期待されます。
まとめ
本稿では、Google Arts & Cultureと福田美術館による「Moving Paintings」プロジェクトについて解説しました。動画生成モデル「Veo」を用いることで、静的な美術品に動きを与え、そこに秘められた物語や、作品が生まれたであろう現実世界を可視化するこの試みは、アート鑑賞体験を変える可能性を秘めています。テクノロジーと文化が融合することで生まれる新しい表現の形として、今後の展開が注目されます。