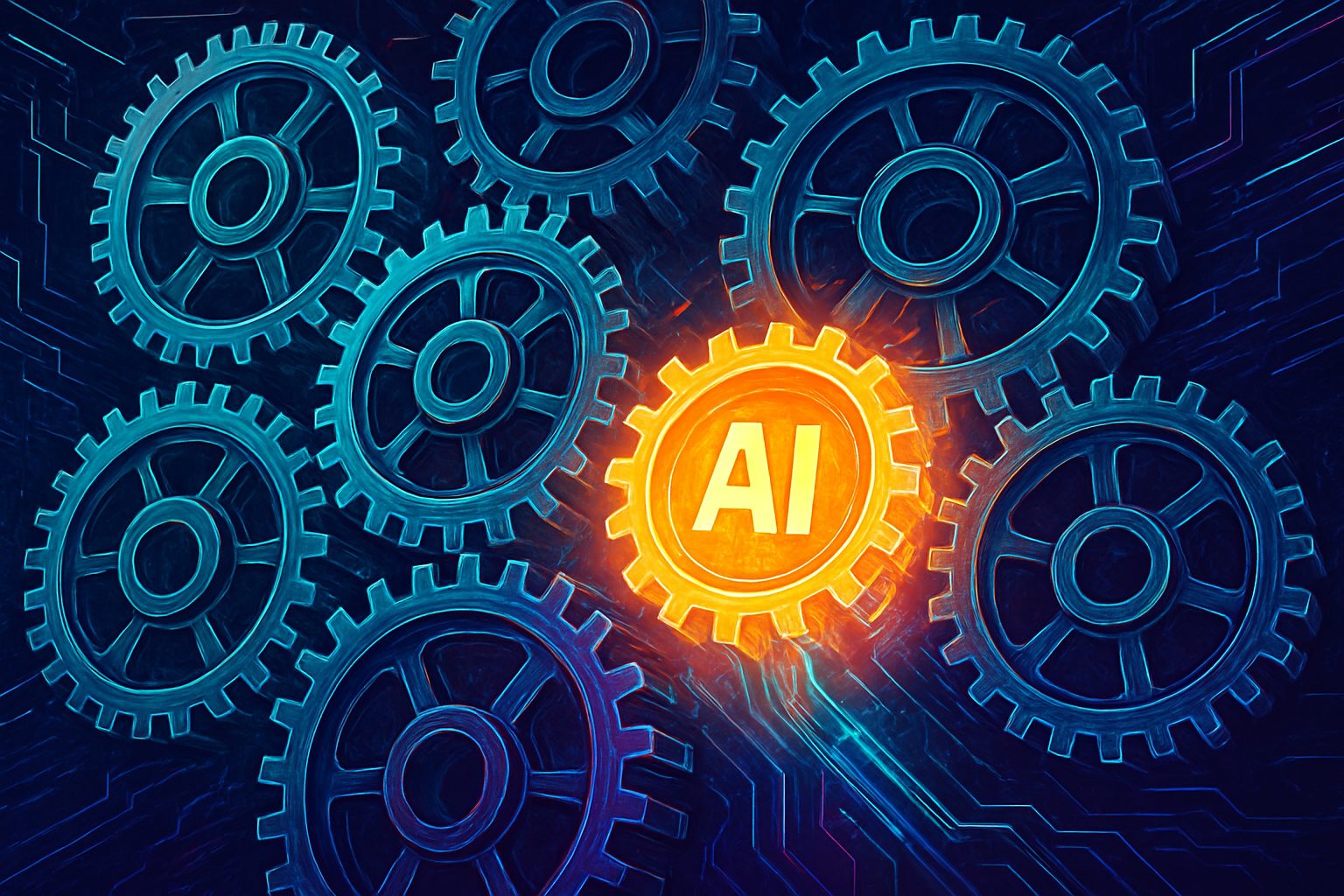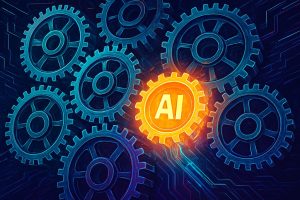はじめに
自律的にタスクをこなすAIエージェントは、業務効率を大きく向上させる可能性を秘めていますが、その導入は単純なものではありません。重要なのは、新しい技術で既存のものを全て置き換えるのではなく、これまで築き上げてきた資産を活かしながら、分析や推奨を行う「インテリジェンスのシステム」から、具体的な行動を起こす「アクションのシステム」へと進化させるための考え方です。
本稿では、IBMの公式ブログ「THINK」に2025年8月8日付で掲載された記事「Businesses have systems of intelligence. Now they should move to systems of action」を基に、企業がAIエージェントを導入する際の現実的なアプローチについて解説します。
参考記事
- タイトル: Businesses have systems of intelligence. Now they should move to systems of action
- 著者: Anabelle Nicoud
- 発行元: IBM
- 発行日: 2025年8月8日
- URL: https://www.ibm.com/think/news/agent-orchestration-systems-action
要点
- 企業の情報システムは「記録」「エンゲージメント」「インテリジェンス」のシステムを経て、自律的に行動を起こす「アクションのシステム」へと進化の段階にある。
- AIエージェント導入の成功の鍵は、既存の有効な業務プロセスや自動化システムを置き換えるのではなく「拡張」することである。
- 安易な置き換えは、かえって業務を悪化させる「エージェント・マイナス」に陥る危険性がある。
- 今後は、多数のエージェントを連携・調整する「オーケストレーション」が重要となり、そのための5つのコア機能と通信プロトコルの標準化が不可欠である。
詳細解説
「インテリジェンス」から「アクション」へ:企業システムの進化
企業のITシステムは、これまで段階的に進化してきました。最初は取引などを記録する「記録のシステム(Systems of Record)」から始まり、顧客との接点を持つ「エンゲージメントのシステム(Systems of Engagement)」、そしてデータを分析して洞察を得る「インテリジェンスのシステム(Systems of Intelligence)」へと発展してきました。
しかし、IBMのBruno Aziza氏が指摘するように、インテリジェンスのシステムは「有用であるものの、十分ではない」のが現状です。分析や推奨を行うだけでは、最終的なビジネス成果には直接結びつきません。そこで次の段階として、洞察に基づき自律的に行動を起こし、ビジネスの収益に直接貢献する「アクションのシステム」への移行が求められています。これを実現する中核技術が、自律型システムであるAIエージェントなのです。
AIエージェント導入の落とし穴:「エージェント・マイナス」という考え方
AIエージェントの導入を検討する際、「既存のシステムを全て新しいAIエージェントに置き換えればよい」と考えてしまうのは、よくある誤解です。Aziza氏はこのアプローチに警鐘を鳴らしています。なぜなら、企業には既に長年かけて最適化され、うまく機能しているAIや自動化の仕組みが組み込まれているからです。
例えば、銀行のローン承認プロセスを考えてみましょう。このプロセスは、明確なルールに基づいて行われる「決定論的な」業務です。ここに、確率に基づいて判断を行うAIエージェントを単純に導入すると、かえって不確実性が増し、プロセスの精度や信頼性が低下する可能性があります。
このように、既存の有効なシステムを置き換えた結果、より悪い結果をもたらしてしまう状態を、Aziza氏は「エージェント・マイナス」と呼んでいます。成功への道は、既存のプロセスを排除することではなく、AIエージェントを使って既存のプロセスを「拡張」し、強化していくことなのです。
未来の姿:エージェントの「オーケストレーション」
AIエージェントの活用が進むと、将来的には多くの従業員が自分専用のエージェントを構築したり、カスタマイズしたりする時代が来ると予測されています。そうなると、社内には無数のエージェントが存在することになります。
ここで新たな課題が生まれます。それは、「誰が(どのエージェントが)何を行い、誰がデータを収集し、誰がプロセスを監督するのか?」という問題です。この無数のエージェントを連携させ、協調して動作させるための仕組み、それが「オーケストレーション」です。
オーケストレーション実現のための5つの柱
Aziza氏は、エージェントのオーケストレーションを成功させるためには、企業が構築すべき5つのコア機能があると述べています。
- マルチエージェント・コラボレーション: 複数のエージェントが互いに連携し、協力してタスクを遂行する能力。
- クロスエコシステム統合: 社内だけでなく、パートナー企業など外部のエコシステムとも連携できる能力。
- 既存ツール・ルールとの連携: 既に社内で使われているツールや、定められているビジネスルールとスムーズに連携する能力。
- 監督と制御: エージェントの活動を人間が監視し、必要に応じて制御できる仕組み。
- エージェントOps (Agents Ops): エージェントの開発、テスト、展開、運用を管理するための専門的な運用レイヤー。
これらの機能を整備することが、エージェント戦略を推進する上での重要な基盤となります。
標準化がもたらす未来:HTTPの登場との比較
オーケストレーションを機能させるためには、技術的な「標準化」が不可欠です。人間が共通言語で話すように、エージェント同士も共通のプロトコル(通信規約)で対話できなければ、効果的な連携は望めません。
現在、Googleの「Agent2Agent Protocol」やIBMの「ACP (Agent Communication Protocol)」など、様々な標準化の取り組みが進められています。記事では、この状況を「HTTPが登場する前のインターネット」に例えています。かつて、HTTPという標準規約が生まれたことでワールド・ワイド・ウェブが爆発的に普及したように、エージェント間の通信が標準化されれば、その影響は個々のエージェントの能力を掛け合わせ、イノベーションを飛躍的に加速させる可能性があるのです。
まとめ
本稿では、IBMの記事を基に、企業がAIエージェントを導入する上での重要な視点について解説しました。
AIエージェントの導入は、単なる技術の刷新ではありません。最も重要なのは、「置き換え」ではなく「拡張」という発想です。自社の強みである既存のシステムやプロセスを尊重し、それらをAIエージェントによってさらに強化していくことが、失敗を避け、真の価値を創出する鍵となります。
そして、その先にある多数のエージェントが協調して動作する未来を見据え、「オーケストレーション」の仕組みと、その基盤となる標準化に目を向けて準備を進めていくこと。これが、これからの企業に求められる次なる一手と言えるでしょう。