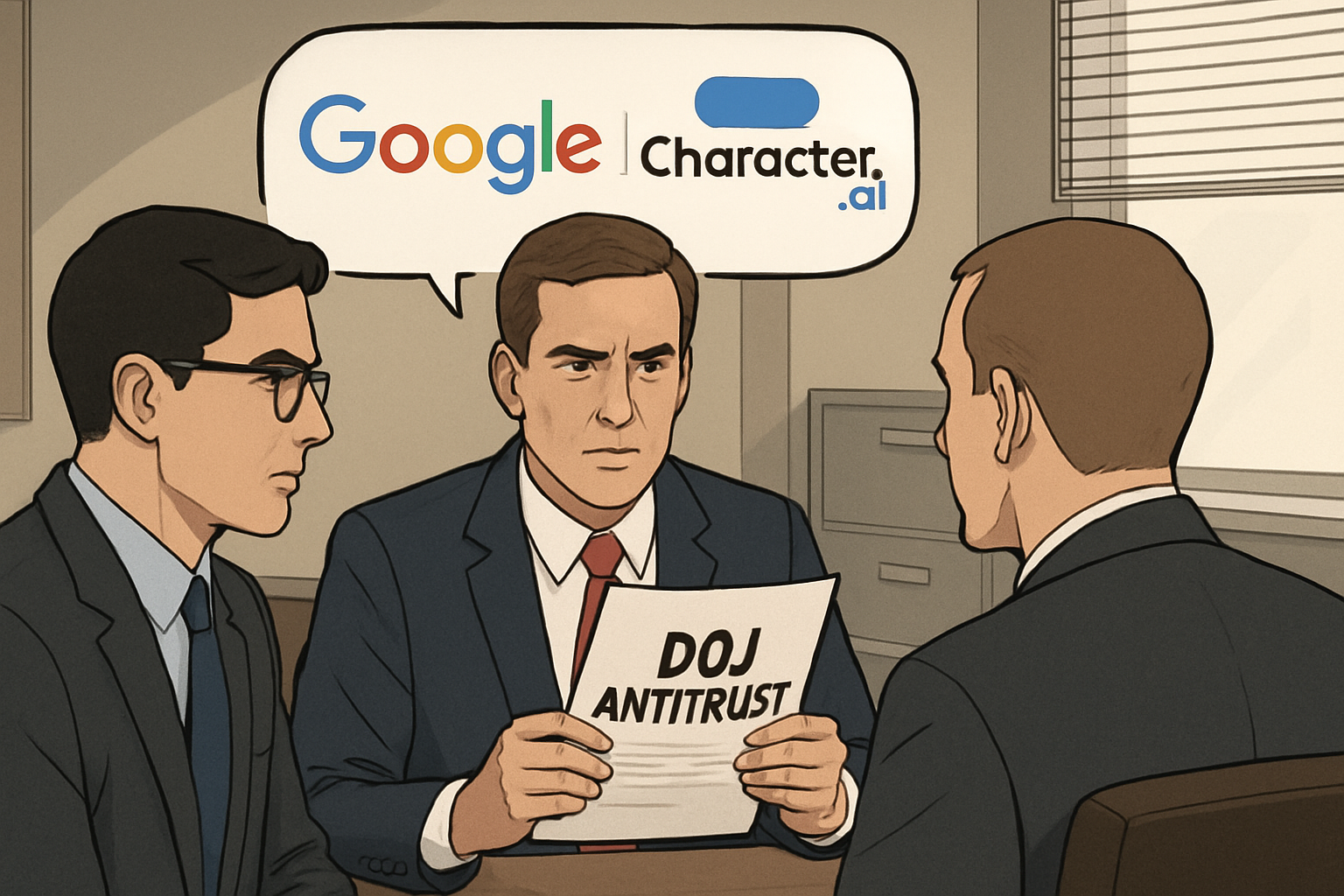はじめに
本稿では、ロイター通信が2025年5月23日に報じた「Google faces DOJ probe over Character.AI deal, Bloomberg Law reports」という記事をもとに、GoogleとAIスタートアップCharacter.AIとの契約に対する米国司法省の独占禁止法調査について解説します。
引用元記事
- タイトル:Google faces DOJ probe over Character.AI deal, Bloomberg Law reports
- 発行元:Reuters
- 発行日:2025年5月23日
- URL:https://www.reuters.com/business/google-faces-doj-probe-over-deal-ai-tech-bloomberg-law-reports-2025-05-22/

要点
- 米国司法省(DOJ)は、GoogleとAIスタートアップCharacter.AIとの契約が独占禁止法に違反する疑いで調査を開始した。
- 調査の焦点は、GoogleがCharacter.AIの技術ライセンス取得と共同創業者雇用という形で、実質的な企業買収でありながら政府の正式な合併審査を意図的に回避したか否かである。
- Character.AIは、大規模言語モデル(LLM)技術を持つ注目のAI企業であり、その共同創業者は元Google社員である。
- Google側は、Character.AIへの出資はなく独立した企業であると主張している。
- 背景には、AI分野における巨大テック企業の競争激化と、それに対する規制当局の監視強化がある。
詳細解説
米国司法省(DOJ)による調査の背景
今回、GoogleとCharacter.AIの契約に米司法省(DOJ)が調査のメスを入れた背景には、いくつかの重要なポイントがあります。
独占禁止法とは何か?
まず、独占禁止法について簡単にご説明します。これは、公正な市場競争を保護し、特定の企業による市場支配や不当な取引制限を防ぐための法律です。市場が健全に機能することで、消費者はより良い製品やサービスをより安価に手に入れることができ、また、新しい企業が市場に参入しやすくなり、技術革新も促進されると考えられています。今回のケースでは、Googleのような巨大企業がその市場支配力を不当に利用していないか、という点が問われています。
なぜGoogleの契約が問題視されるのか?
巨大IT企業が、将来有望なスタートアップの革新的な技術や優秀な人材を、契約や買収を通じて囲い込むことは、市場の競争を阻害し、結果として技術の寡占化を進めるのではないかという懸念が常にあります。特に、人工知能(AI)分野は、今後の産業や社会のあり方を大きく変える可能性を秘めた重要技術であり、その開発競争は熾烈を極めています。規制当局は、この分野で特定の企業が不当に優位な立場を築くことに対して、強い警戒感を持っています。
「合併審査逃れ」の疑い
通常、企業が一定規模以上の合併や買収(M&A)を行う際には、独占禁止法に基づき、事前に規制当局(米国ではDOJや連邦取引委員会FTC)に届け出て、その承認を得る必要があります。これは、合併によって市場の競争が不当に制限されないか審査するためです。
今回のGoogleとCharacter.AIの契約は、報道によれば、Character.AIの株式を取得する形での買収ではなく、技術のライセンス契約と主要な人材の雇用という形を取っています。しかし、DOJは、この形式が実質的にはCharacter.AIの持つ重要な技術やノウハウ、そしてそれを生み出したキーパーソンをGoogleが取り込むことになり、事実上の買収に近い効果をもたらしつつ、正式な合併審査を回避する意図があったのではないかと疑っているようです。
Character.AIとは? Googleとの関係性
今回の調査の対象となっているCharacter.AIと、Googleとの関係について見ていきましょう。
Character.AIの概要
Character.AIは、ユーザーが歴史上の人物、アニメのキャラクター、あるいは自身で作成したオリジナルのキャラクターなど、様々なペルソナを持つAIチャットボットと対話できるプラットフォームを提供しているスタートアップ企業です。その自然で人間らしい会話能力の高さから、多くのユーザーを獲得しています。
Googleとの契約内容
報道によると、Googleは昨年、Character.AIとの間で、同社が持つLLM技術に関する非独占的なライセンス契約を結びました。これにより、GoogleはCharacter.AIの技術を自社の製品やサービスに活用できるようになったとみられます。「非独占的」とは、Character.AIがGoogle以外の企業にも同様のライセンスを与えることができる、という意味です。
さらに重要な点として、GoogleはCharacter.AIの共同創業者であるノーム・シャジア氏(Noam Shazeer)とダニエル・デ・フレイタス氏(Daniel De Freitas)を雇用したと報じられています。この二人は、かつてGoogleに在籍し、現在のLLM技術の基礎ともなった重要な論文「Attention Is All You Need」の共著者でもあるなど、AI分野で世界的に著名な研究者です。彼らが開発した技術や知見が、Character.AIの強みの中核となっていると考えられます。
Googleの主張
この件に関してGoogleの広報担当者は、「Character.AIの人材が当社に加わったことは喜ばしいが、当社はCharacter.AIの株式を保有しておらず、彼らは独立した会社のままである」とコメントしています。つまり、資本関係はなく、あくまで技術ライセンスと人材採用の契約であるという立場です。しかし、規制当局は、契約の形式だけでなく、その実質的な影響力や市場への効果を重視する傾向にあります。
技術的なポイントと市場への影響
今回の調査が注目される背景には、AI技術、特にLLMを巡る技術的なポイントと市場への影響があります。
AI技術の囲い込み懸念
Character.AIが持つ独自のLLM技術や、それを開発した世界トップクラスのエンジニアがGoogleに合流することで、革新的なAI技術が特定の巨大企業に集中・囲い込まれるのではないかという懸念が生じます。これにより、他の企業や研究機関が同様の技術開発を行う際のハードルが上がり、結果としてイノベーションの多様性が失われる可能性があります。
「アクハイヤー(Acqui-hire)」との類似性
今回のGoogleの動きは、「アクハイヤー(Acqui-hire)」と呼ばれる戦略に類似していると指摘されることがあります。アクハイヤーとは、「Acquisition(買収)」と「Hire(雇用)」を組み合わせた造語で、企業が製品やサービスそのものよりも、そこに所属する優秀な人材を獲得することを主目的として行う買収のことです。特に競争の激しいIT業界では、優秀なエンジニアや研究者の獲得は企業の競争力を左右する重要な要素であり、アクハイヤーは珍しいことではありません。今回のケースも、Character.AIの技術そのものに加え、それを生み出したシャジア氏とデ・フレイタス氏というトップタレントの獲得が大きな目的であった可能性が考えられます。
生成AI市場の競争環境
生成AIの分野では、Googleだけでなく、マイクロソフト(Inflection AIとの提携)、アマゾン(AIスタートアップAdeptの共同創業者らを雇用)など、他の巨大テック企業も同様に、有望なAIスタートアップとの提携や人材獲得を積極的に進めています。これらの動きは、AI技術開発競争の激しさを物語っていますが、同時に、一部の巨大企業による市場の寡占化が進むリスクもはらんでいます。規制当局は、こうした個別の契約だけでなく、市場全体の競争環境に与える影響を注視していると考えられます。
今後の展望
最後に、この調査が今後どのように進展し、私たちにとってどのような意味を持つのかを考えてみましょう。
調査の行方
ロイターの記事によれば、DOJによる今回の調査はまだ初期段階であり、必ずしもGoogleに対する法的措置(例えば、契約の差し止めや変更命令など)に至るとは限りません。しかし、米国ではバイデン政権下で巨大IT企業に対する規制を強化する動きが鮮明になっており、今回の調査もその流れの一環と捉えることができます。仮にDOJがこの契約を問題視し、何らかの措置を講じることになれば、今後のAI業界における企業の提携戦略やM&Aのあり方に大きな影響を与える可能性があります。
まとめ
本稿では、GoogleとAIスタートアップCharacter.AIとの契約に対し、米国司法省が独占禁止法の観点から調査を開始したというニュースについて、その背景、技術的なポイント、そして私たちへの影響を解説しました。この調査は、AIという最先端技術分野における巨大IT企業の市場支配力と、それを抑制しようとする規制当局の動きが交錯する現代的な事象と言えます。特に、株式取得を伴わない技術ライセンス契約とキーパーソンの雇用というスキームが、実質的な企業買収と見なされ、独占禁止法上の審査対象となる可能性を示唆している点は、今後の企業戦略を考える上で非常に重要です。AI技術の急速な発展がもたらす恩恵を最大限に享受するためにも、その基盤となる市場の公正な競争環境がどのように守られていくのか、引き続き注目していく必要があります。