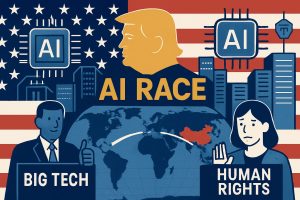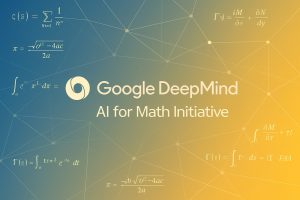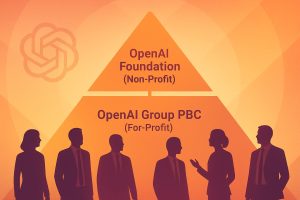はじめに
近年、世界の技術開発競争の中心となっている人工知能(AI)、その覇権を巡り、アメリカと中国の動きがますます活発化しています。2025年7月、中国は上海で開催された世界最大級のAIカンファレンスで、AIに関する新たな国際戦略を発表しました。これは、数日前にアメリカが独自のAI戦略を打ち出した直後のことであり、両国の競争が新たな段階に入ったことを示唆しています。
本稿では、各国メディアが報じた内容を基に、中国が新たに提唱したAI戦略「グローバルAI協力機関」構想を深掘りします。その背景にある米国の戦略との対比や、半導体を巡る技術的な対立、そして国際的なルール作り(AIガバナンス)の課題について解説します。
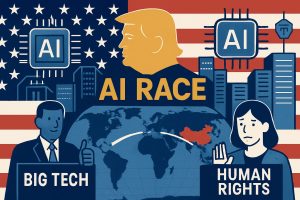

参考記事
- 発行元: CNBC
- タイトル: China releases AI action plan days after the U.S. as global tech race heats up
- 発行日: 2025年7月26日
- URL: https://www.cnbc.com/2025/07/26/china-ai-action-plan.html
- 発行元: Reuters
- タイトル: China proposes new global AI cooperation organisation
- 発行日: 2025年7月26日
- URL: https://www.reuters.com/world/china/china-proposes-new-global-ai-cooperation-organisation-2025-07-26/
- 発行元: The Guardian
- タイトル: China calls for global AI cooperation days after Trump administration unveils low-regulation strategy
- 発行日: 2025年7月26日
- URL: https://www.theguardian.com/technology/2025/jul/26/china-calls-for-global-ai-cooperation-days-after-trump-administration-unveils-low-regulation-strategy
要点
- 中国は2025年7月26日、上海の世界人工知能会議(WAIC)で、グローバルなAI協力機関の設立と、国際協力を呼びかける行動計画を発表した。
- この発表は、アメリカが自国のAI産業保護と中国への対抗を鮮明にしたAI戦略を発表した直後に行われ、米中間の技術覇権争いを色濃く反映している。
- 中国は、発展途上国を含む「グローバルサウス」との連携を強調し、AI技術のオープンな共有を掲げることで、米国の同盟国中心のアプローチとは異なる多国間協力の枠組みを主導しようとしている。
- 背景には、米国による先端半導体の対中輸出規制がある。中国はこれに対抗し、国産技術の開発を急いでいる。
- AIの開発とセキュリティリスクのバランスを取る「AIガバナンス」が世界的な重要課題となっており、中国は国際的なルール形成に積極的に関与する姿勢を示している。
詳細解説
中国が打ち出した「グローバルAI協力」構想
2025年7月26日、中国の李強首相は、上海で開催された世界人工知能会議(WAIC)の冒頭演説で、AIに関する国際的な協力機関を設立する構想を明らかにしました。この構想は、AI技術の開発やルール作り(ガバナンス)において、国際的な協調を深めることを目的としています。
李首相は、AIが一部の国や企業による「排他的なゲーム」になることへの懸念を表明し、すべての国が平等にAIを利用できる権利を持つべきだと主張しました。特に、アジアやアフリカ、ラテンアメリカなどの発展途上国を指す「グローバルサウス」との技術共有や開発支援に意欲を示しています。これは、アメリカが同盟国との連携を強化する戦略に対抗し、独自のパートナーシップ網を構築しようとする狙いがあると考えられます。
また、中国は国内政策として「AIプラス」計画を推進しており、AIをあらゆる産業に統合することを目指しています。この国内での成功体験を、国際協力の場でアピールしていく戦略です。
アメリカの戦略との鮮明な対比
中国の発表の数日前、アメリカのトランプ政権は、自国のAI産業の優位性を維持するための行動計画を発表しました。その内容は、同盟国へのAI技術の輸出を拡大し、アメリカの技術が国際標準となることを目指すもので、明確に中国を意識した戦略です。
CNBCの記事で専門家が「2つの陣営が形成されつつある」と指摘しているように、世界は2つの異なるアプローチに分かれようとしています。
- アメリカの陣営: 日本やオーストラリアなどの同盟国と連携し、技術的な優位性と価値観を共有する国々で協力体制を固める。
- 中国の陣営: 「一帯一路」構想の参加国やグローバルサウスを中心に、より幅広い国々を巻き込む多国間協力の枠組みを目指す。
このように、AIを巡る動きは単なる技術開発競争ではなく、国際的な影響力をかけた地政学的な競争の様相を呈しています。
技術覇権の鍵を握る「半導体」
この米中対立の根底には、AIモデルの学習に不可欠な先端半導体(AIチップ)を巡る競争があります。アメリカは2022年以降、安全保障上の懸念を理由に、NVIDIAなどが製造する高性能なAIチップの中国への輸出を厳しく規制してきました。
この規制は、中国のAI開発にとって大きな障害となっています。しかし、中国はこれに屈することなく、ファーウェイ(Huawei)やアリババ(Alibaba)といった国内の巨大テック企業を中心に、国産AIチップの開発を急ピッチで進めています。NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが中国の国産チップを「手ごわい(formidable)」と評価したように、その技術力は着実に向上していると見られます。
半導体の供給不足や人材交流の制限は、AI開発における世界的なボトルネックであり、中国の李首相もこの点を課題として挙げています。
世界共通の課題「AIガバナンス」
AI技術が急速に進化する一方で、その利用に伴うリスクも増大しています。偽情報の拡散、雇用の喪失、プライバシーの侵害、さらには技術が人間のコントロールを離れる可能性など、解決すべき課題は山積みです。
李首相は演説で、「開発と安全性のバランスをどう取るかは、社会全体のコンセンサスが緊急に必要だ」と述べ、AIガバナンスの重要性を強調しました。現在、AIに関する規制やルールは国によって異なり、「断片的」な状況です。中国は、国際的に合意されたガバナンスの枠組みを早急に形成すべきだと主張しており、そのプロセスで主導権を握りたいという思惑がうかがえます。
まとめ
本稿では、中国が新たに発表したAI戦略について、米中対立の文脈を交えながら解説しました。中国の「グローバルAI協力機関」構想は、単なる技術協力の呼びかけではありません。それは、アメリカ主導の技術秩序に対抗し、グローバルサウスを巻き込みながら新たな国際的な枠組みを構築しようとする、壮大な地政学的戦略の一環です。
この動きの中心には、AI開発の生命線である半導体を巡る攻防があり、同時に、AIの安全な利用を目指す国際的なルール作り(AIガバナンス)という世界共通の課題が存在します。
二大国の間でどのような立ち位置を取り、自国のAI技術をどう発展させていくのか。そして、国際的なルール形成にどう貢献していくのか。技術開発と国際協調の両面で、日本の戦略的な判断がこれまで以上に重要になっています。