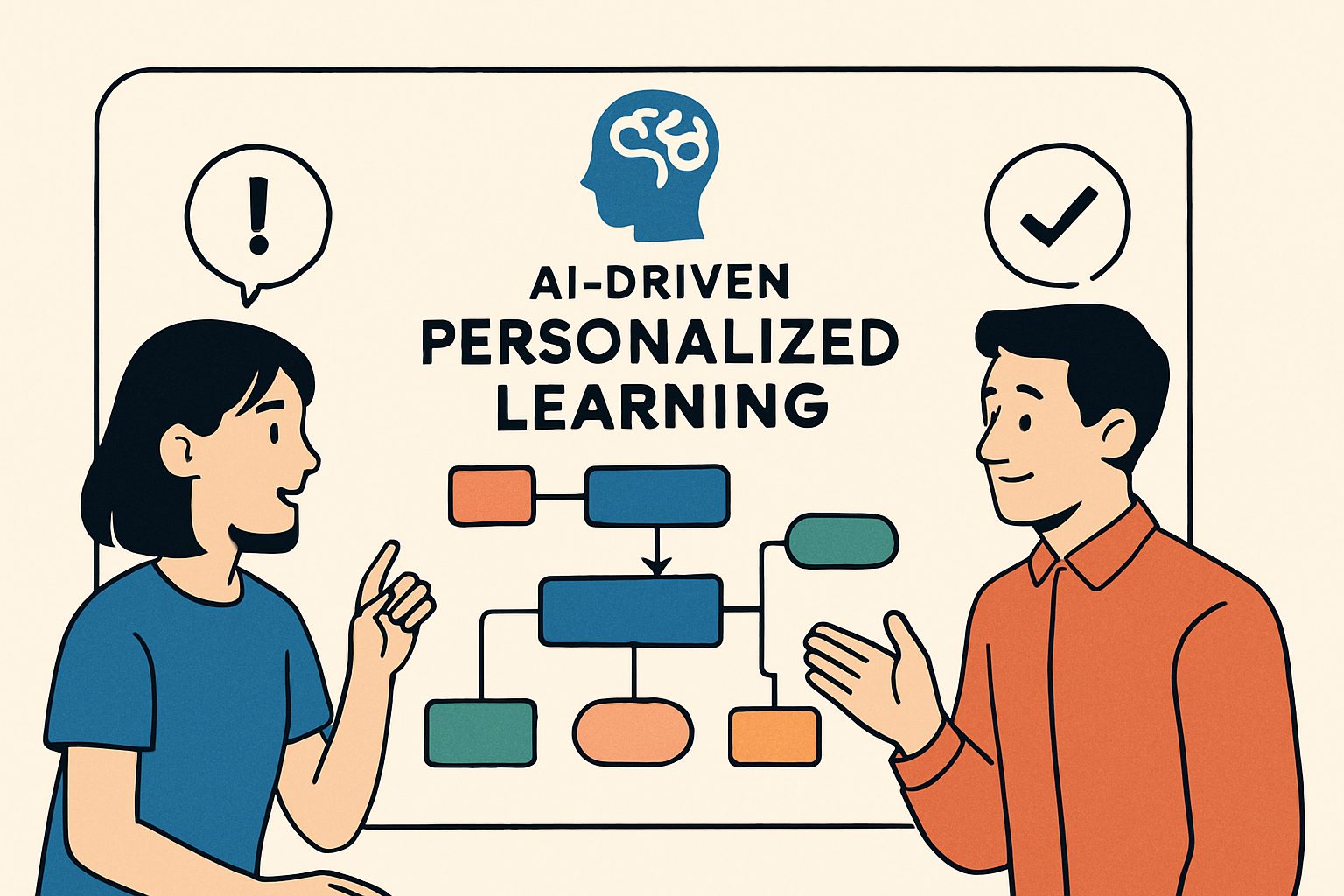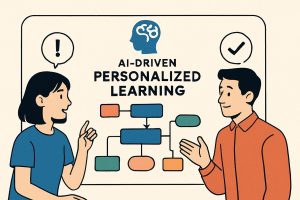はじめに
米国のオンラインコミュニティカレッジCampusが2025年10月、AI学習支援アプリ「Sizzle AI」を買収しました。Sizzle AIは、元Facebook AI責任者Jerome Pesenti氏が創業したサービスで、今回の買収によりPesenti氏はCampusのCTO(最高技術責任者)に就任します。本稿では、CNBCのインタビュー動画をもとに、この買収の背景と、AIと人間のコーチを組み合わせた教育モデルについて解説します。
参考記事
- タイトル: Campus founder Tade Oyerinde on acquisition of Sizzle AI, future of AI and higher education
- 発行元: CNBC
- 発行日: 2025年10月10日
- URL: https://www.youtube.com/watch?v=iGk5wJo1XB0
要点
- オンラインコミュニティカレッジCampusがAI学習支援アプリ「Sizzle AI」を買収し、創業者Jerome Pesenti氏がCTOに就任した
- Sizzle AIは答えを直接教えるのではなく、学生の理解度ギャップを分析し、個別最適化された学習経路を提供する
- 米国の2年制大学の卒業率は27%にとどまり、3分の2の学生が平均5,700ドルの学生ローンを抱えて退学している
- Campusは50人の学生に1人の人間コーチを配置し、AIと人間を組み合わせた支援体制を構築している
- 学費は年間10,000ドル以下に設定され、86%の学生がPell Grant(連邦政府奨学金)により自己負担なしで通学できる
詳細解説
Campusの事業モデルとSizzle買収の背景
Campusは、プリンストン大学、UCLA、ニューヨーク大学などトップクラスの大学の教授陣がオンラインで授業を提供するコミュニティカレッジです。創業者のTade Oyerinde氏によれば、Campusは無借金で最初の2年間の大学教育を受けられることを特徴としています。
今回のSizzle AI買収について、Oyerinde氏は「授業が終わった後、学生が行き詰まらずに最高の教材から学び続けるにはどうすればよいか」という課題意識から決断したと語っています。現在のCampusでは、授業後に学生が頼れるのは教科書だけという状況でした。Sizzle AIの統合により、授業外の学習支援を大幅に強化できると期待されています。
Sizzle AIの仕組み:答えを教えず、学習を支援する
Sizzle AIの創業者Jerome Pesenti氏は、元Facebook AI責任者という経歴を持つ人物です。Pesenti氏は、Sizzle AIについて「人々が何でも学べるようAIでサポートするアプリです。答えを教えるのではなく、学ぶべきことを学べるよう支援します。学習者のギャップを見つけ出し、そこから引き上げて前進させます」と説明しています。
技術的には、複数の大規模言語モデル(LLM)を組み合わせて使用しています。Pesenti氏によれば、「数学が得意なモデル、科学が得意なモデルなど、それぞれの強みを組み合わせて、ユーザーが使いやすいインターフェースを作っています」とのことです。また、これらのモデルに対してファインチューニング(追加学習)を行い、学生の理解状況を詳細に把握できるようカスタマイズしているそうです。
現在は主にオープンソースの教材を使用していますが、Campusとの統合後は、Campus所属の教授陣が作成した教材を活用する計画です。
個別最適化された学習経路の提供
Oyerinde氏は、Sizzle AIの技術的な強みについて詳しく説明しています。まず、学生の理解度を「概念の原子単位」まで細かく分解して評価します。その評価に基づいて、初日から90日目まで、各学生に完全にパーソナライズされた学習経路を作成するとのことです。
この仕組みの特徴は、すでに理解している概念については繰り返さず、次のステップに進める点にあります。Oyerinde氏は「他のどの大学でもこのようには機能していません。すべての学生が、異なるバックグラウンドから来ているにもかかわらず、まったく同じ課題、まったく同じ演習を行っています」と指摘し、Campusが「授業のすべてのステップが各学生にパーソナライズされた初の大学」になると述べています。
AIは教授を代替するのか:人間の役割の重要性
インタビューでは、AIが教授や大学院生を代替するのではないかという質問も出ました。これに対してOyerinde氏は「決して代替しません」と明言しています。Sizzle AIの役割はあくまで授業後の学習補助であり、授業自体はすべてライブのオンライン授業として提供されます。
現在、学生が授業後に頼れるのは教科書か、あるいは単に答えを教えてくれるChatGPTのようなツールだけです。Sizzle AIは、そうしたツールとは異なり、学習者の弱点を把握し、前提知識の不足を補いながら段階的に導くことを目指しています。例えば、「この部分が理解できていないようですね。もう一度やりましょう」といった形で、学習者を丁寧にサポートするわけです。
人間のコーチが果たす役割
AIツールの充実だけでは、卒業率の向上には不十分だとOyerinde氏は考えています。インタビューでは、「高いモチベーションを持った人々が必要です」という指摘がありました。これに対してOyerinde氏は、50人の学生に対して1人の人間コーチを雇用していることを強調しています。
Oyerinde氏は自身の家族を例に出し、「ナイジェリア人の母親のような存在です。サボっていたら、私がお尻を叩きます。泣く肩が必要なときは、そこにいて励まし、ゴールラインまで引っ張っていくコーチのような存在です」と説明しています。AIによる学習支援と人間コーチによる動機付けの両輪が、卒業率向上のカギだと考えられているようです。
米国の大学教育が抱える深刻な課題
Oyerinde氏が今回の買収を決断した背景には、米国の高等教育システムが抱える深刻な問題があります。インタビューによれば、米国の2年制大学の卒業率はわずか27%にとどまっています。卒業できない学生、つまり3分の2の学生は、平均5,700ドルの学生ローンを抱えたまま退学しているとのことです。
Oyerinde氏は「この問題をコントロール下に置かなければ、若者たちは諦めてしまいます」と危機感を表明しています。また、「この国を軌道に戻すためには、学生ローンをなくし、『もう学生ローン債務はなしです。2兆ドルは許容できません』と言う必要があります。高等教育システムを再び機能させ、若者を実践的なスキル訓練に導く必要があります」と述べています。
Campusの経済モデル――Pell Grantの活用
Campusの経済モデルは、Pell Grant(ペルグラント)と呼ばれる連邦政府の奨学金制度を活用しています。Oyerinde氏によれば、「米国にはすでに無料大学プログラムがあります。それがPell Grantです」とのことです。共和党が多数を占める上院も、この制度への資金を年間10,000ドルに増額する決定を下したそうです。
Campusの学費は年間10,000ドル以下に設定されているため、86%の学生は自己負担なしで通学できるとのことです。2年間Campusで学んだ後、学生はニューヨーク大学、UCLA、プリンストン大学などの4年制大学に編入し、最後の2年間を修了する仕組みです。
※見解:日本の高等教育への示唆
今回のインタビューで特に印象的だったのは、創業者たちが自社の価値を技術そのものよりも、トップクラスの大学とのつながりと人間のコーチング体制に置いている点です。AIはあくまで補助的な役割であり、教授やコーチといった人間との関わりが学習を継続し、卒業に至る上で不可欠だという認識が明確に示されています。
また、米国では卒業そのものが難しく、退学する学生のほうが多数派という現実があります。そのため、学習へのモチベーションをどう維持するかが前提として議論されています。日本では逆に卒業は比較的容易ですが、その分、モチベーションを失ったまま学習機会を十分に活用できず卒業してしまうケースも多いのではないでしょうか。
米国のような人間コーチによる伴走支援と、AIによる個別最適化された学習支援を組み合わせたモデルは、日本の高等教育においても参考になるかもしれません。特に、社会人のリスキリングや生涯学習の文脈では、こうした支援体制の重要性が今後さらに高まっていくと思われます。
まとめ
CampusによるSizzle AI買収は、AIと人間のコーチングを組み合わせた新しい教育モデルを示すものです。答えを教えるのではなく学習を支援するAI、50人に1人という手厚い人間コーチ、そして無借金で学べる経済モデル。これらの要素が組み合わさることで、米国の低い大学卒業率という課題に挑戦しています。日本においても、学習支援のあり方を考える上で参考になる事例ではないでしょうか。