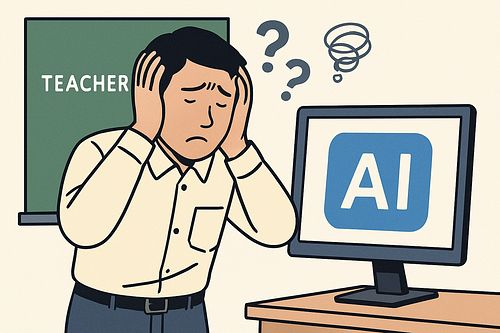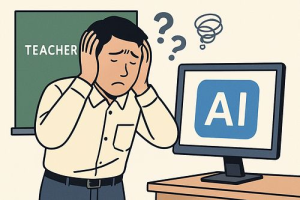はじめに
米国の非営利団体Center for Democracy and Technologyが2025年10月8日に公表した報告書「Schools’ Embrace of AI Connected to Increased Risks」が、教育現場におけるAI利用の急速な拡大と、それに伴う深刻な懸念を明らかにしました。本稿では、Education Weekが同日報じたこの報告書の内容をもとに、米国の学校現場で何が起きているのか、そしてどのような課題があるのかを解説します。
参考記事
- タイトル: Rising Use of AI in Schools Comes With Big Downsides for Students
- 著者: Jennifer Vilcarino & Lauraine Langreo
- 発行元: Education Week
- 発行日: 2025年10月8日
- URL:https://www.edweek.org/technology/rising-use-of-ai-in-schools-comes-with-big-downsides-for-students/2025/10
要点
- 2024-25学年度には、教師の85%と生徒の86%がAIを利用しており、教育現場でのAI活用が急速に拡大している。
- 生徒の半数がAI利用によって教師との関係性が希薄化していると感じており、教師の70%が批判的思考力や調査能力の低下を懸念している。
- 教師の69%がAIによって教育方法が改善されたと回答する一方で、71%が生徒の提出物の真正性を判断する負担が増えたと回答している。
- 学校や学区からAIに関する研修や情報提供を受けた教師と生徒はそれぞれ48%にとどまり、急速な利用拡大に対応が追いついていない状況も明らかになった。
- 専門家は、教師への研修とAIリテラシー教育の充実が急務であると指摘している。
詳細解説
AI利用の急速な拡大と教育ツールへの自動統合
Center for Democracy and Technologyの報告書によれば、2024-25学年度には米国の教師の85%、生徒の86%がAIを利用しています。この調査は、6-12学年の公立学校教師、6-12学年の生徒の保護者、9-12学年の生徒を対象に、2025年6月から8月にかけて実施されました。
報告書では、教師によるAI利用の増加の主な理由として、教育ツールにAI機能が自動的に追加されることを挙げています。実際、24%の教師がこのケースに該当すると回答しました。ISTE + ASCDのチーフ・イノベーション・オフィサーであるJoseph South氏は「85%の教師が何らかの形でAIを使用していると聞いても驚きません」と述べています。
教師がAIを活用している主な用途は、カリキュラムやコンテンツ開発(69%)、生徒のエンゲージメント向上(50%)、専門能力開発(48%)、採点ツール(45%)などです。South氏は「AIは教師の仕事をより効率的にすることと、より効果的にすることの2つを実現します。教師の時間を節約できるものは何でも普及するでしょう」と説明しています。
生徒への悪影響と懸念される課題
しかし、AI利用の拡大は深刻な懸念も引き起こしています。報告書の中で最も注目すべき点は、生徒と教師の関係性への悪影響です。生徒の半数が、授業でAIを使用することで教師とのつながりが希薄化していると感じています。また、教師の47%、保護者の50%が、AI利用によって生徒同士のつながりが減少することを懸念しています。
さらに、教師の70%が、AIによって批判的思考力や調査能力が弱まることを心配しています。Center for Democracy and Technologyのエクイティ・イン・シビック・テクノロジー・プロジェクトのディレクターであるElizabeth Laird氏は「多くの人々がAIが教育を変革する可能性を喧伝する中、生徒への悪影響を見過ごしてはなりません」と警告しています。
Laird氏はさらに「私たちの調査は、学校でのAI利用には、大規模なデータ漏洩、テクノロジーによって助長される性的嫌がらせやいじめ、生徒への不公平な扱いといった実際のリスクが伴うことを示しています」と述べています。
教師側のメリットと新たな負担
一方で、報告書は教師側のメリットも示しています。69%の教師がAIツールによって教育方法やスキルが向上したと回答し、59%がAIによってより個別化された学習が可能になったと答え、55%がAIによって生徒と直接関わる時間が増えたと回答しています。
しかし、71%の教師が、生徒によるAI利用が、提出物が本人の作品かどうかを判断する新たな負担を生み出していると回答しています。この点は、AI利用の急速な拡大が教師に与える複雑な影響を象徴しています。
生徒のAI利用の実態とリスク
Common Sense Mediaのシニア・ディレクターであるRobbie Torney氏は、生徒のAI利用は教師とは異なる性質を持つと指摘しています。AIテクノロジーは本来、タスクを迅速に完了するために設計されており、これは教師にとっては管理業務を効率化するメリットがあります。しかし「これらの大規模言語モデルは、必ずしも学習というタスクに最適化されていません。学習はより時間がかかり、努力を要するものです」とTorney氏は説明しています。
生徒がAIを利用している主な用途は、チュータリング(64%)や進路相談(49%)などの学業目的です。しかし、報告書が問題視しているのは、こうした学業に焦点を当てた利用が、すぐに人間関係に関するアドバイス(43%)やメンタルヘルスサポート(42%)を求める利用に転じることです。そして、こうした人間とAIの対話は、しばしば学校が提供するツールやソフトウェアを使って行われています。
Torney氏は「報告書が指摘したリスクの多くは、AI以前から存在していました。しかし、システムへのAIの導入が、そうしたリスクを増幅または悪化させています」と述べています。
研修不足という深刻な問題
報告書が明らかにした最も深刻な問題の1つが、研修と情報提供の不足です。教師と生徒の大多数がすでにAIを利用しているにもかかわらず、学校や学区からAIに関する研修や情報提供を受けたのは、教師と生徒のいずれも48%にとどまっています。
さらに問題なのは、提供される研修や情報の内容が基本的な事項をカバーしていないことです。AIツールを効果的に使用する方法についての指導を受けた教師は29%のみ、AIとは何か、どのように機能するかについての指導を受けた教師は25%、AIシステムの監視と確認方法についての指導を受けた教師はわずか17%でした。
生徒側も同様に、多くが独力でAIを使いこなさなければならない状況です。AI使用に関する学校のポリシーについて指導を受けた生徒は22%、AIを使用するリスクについて指導を受けた生徒は17%、AIとは何か、どのように機能するかについて指導を受けた生徒はわずか12%でした。
専門家が示す解決の方向性
South氏は、生徒と教師が意味のある、洗練された方法でテクノロジーを活用できるようにするには、この基本的な基礎が極めて重要であると述べています。専門家は、学校が教師と生徒に必要な研修と情報を提供するための資金とリソースが必要だと指摘しています。
トランプ政権は教育におけるAI利用の推進を最優先事項の1つとしており、最近では主要なテクノロジー企業が教育団体と提携して、無料の教師研修とリソースを提供し始めています。ただし、一部のAI批判派は、学校が十分な懐疑心を持たずにAIの誇大宣伝に乗っかりすぎているという懸念を表明しています。
それでも、South氏は「学校には、生徒の将来のキャリアにとって重要となるこのテクノロジーについて教える責任があります。私たち全員が、AIの助けを借りて仕事のレベルを上げる可能性を持っています。生徒も同様に仕事のレベルを上げることができますが、教師がそれを正しく行うためには研修が必要です」と述べています。
個人的な見解:日本はさらに深刻な状況か
米国では85%以上という高い利用率が報告されていますが、これは驚くべき数字だと思います。既存の教育サービスにAI機能が自動的に追加されることが利用拡大の一因というのは、確かに納得できます。便利そうなツールが手元にあれば、使ってみたくなるのは自然な流れでしょう。ただ、これは同時に必要なリテラシーを身に着ける前に、利用を開始してしまう可能性が高くなることも意味しています。
半数以上の教師がAIツールの利用によって良い効果を感じているのであれば、今後AIツールの普及は加速することは疑いようがありません。しかし同時に、7割の教師が生徒の提出物がAIによって作成されたものかどうかを判断する負担が増えたと感じている点は、明らかに教育現場でのAIをどのように取り扱うかに課題があることを示しています。
また、生徒が学業目的でAIを使い始めた後、すぐに人間関係やメンタルヘルスに関する相談に利用するようになるという指摘は重要です。これは、AIの適切な利用方法がまだ十分に整理されていないことと、若者にとって人間関係の悩みがいかに切実かということを示しているのではないでしょうか。手近にあるツールが応答してくれるなら、勉強以上に利用したくなるという心理も理解できます。これはAIツールに縁がなかった生徒を学校側が適切な処理なく近づけたことで新たな問題を引き起こすことを助長していると指摘されても仕方がない状態ともいえます。近年AIをめぐる若年層のメンタルヘルスへの悪影響に関する問題提起が活発化していくなかで、学校側も生徒のAIツール利用に関する方針やルールを早急に決定していくことが求められているといえます。
米国では研修不足が問題視されていますが、筆者の知る限り、日本はもっと遅れているのではないかという懸念があります。少なくとも筆者の知人の現役教師(小中高)は、AIツールに関する講習を受けたことがないと話していました。米国では、生徒と教師がAIツールを適切に使いこなすための研修と情報が不足していると指摘されていますが、日本も同様の課題を抱えており、むしろ日本のほうがその問題は深刻かもしれません。
この報告書が提起している課題は、技術の進歩と教育現場の対応のギャップを浮き彫りにしています。AIは確かに教育を変革する可能性を秘めていますが、その前に、適切な研修とガイドラインの整備が急務なのではないでしょうか。
まとめ
米国の学校現場では、教師と生徒の85%以上がAIを利用しており、その急速な拡大が生徒と教師の関係性の希薄化や批判的思考力の低下といった懸念を引き起こしています。最も深刻な問題は、利用が先行し、研修や情報提供が追いついていないことです。専門家は教師への研修とAIリテラシー教育の充実を訴えていますが、この課題は米国だけでなく、日本を含む多くの国々が直面する共通の課題かもしれません。AIが教育にもたらす可能性を最大化するためには、まず基盤となる研修体制の整備が必要なのではないでしょうか。