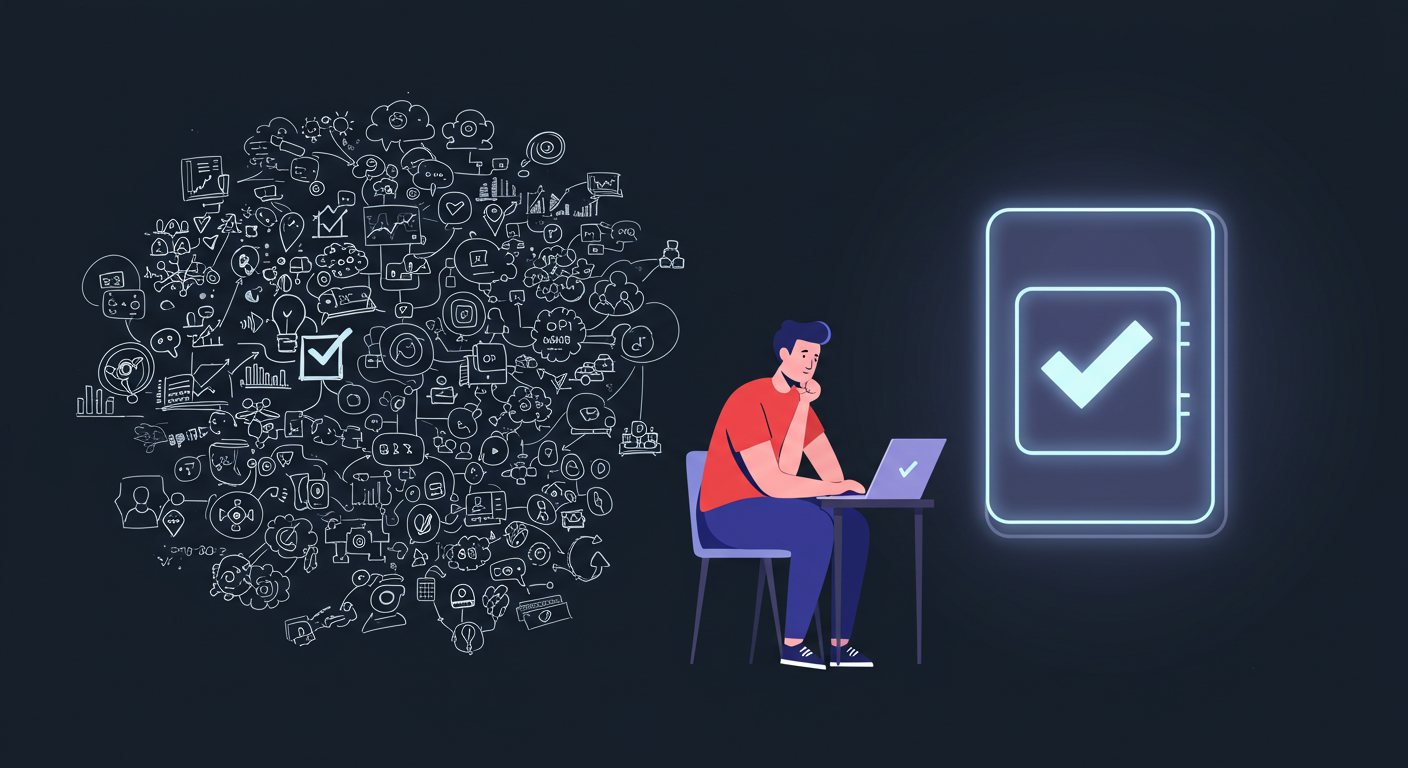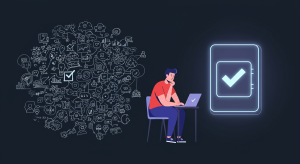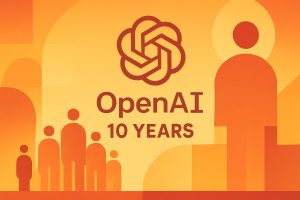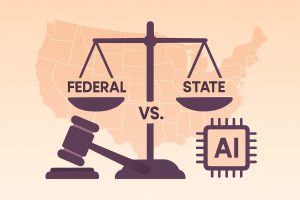はじめに
近年、ChatGPTをはじめとする生成AI(Generative AI)の進化は目覚ましく、私たちの仕事や生活に大きな変化をもたらしています。税務処理から文章作成、さらには悩み相談まで、AIはこれまで人間が行ってきた知的作業を肩代わりしてくれるようになりました。しかし、その一方で、AIへの依存が人間の知的能力、特に批判的思考力や記憶力、創造性を低下させるのではないかという懸念の声も上がっています。
本稿では、ヘレン・トムソン氏による記事「‘Don’t ask what AI can do for us, ask what it is doing to us’: are ChatGPT and co harming human intelligence?」を元に、AIが人間の知性に与える影響について、専門家の意見や研究結果を交えながら、分かりやすく解説します。
引用元情報:
- 記事タイトル: ‘Don’t ask what AI can do for us, ask what it is doing to us’: are ChatGPT and co harming human intelligence?
- 発行元: The Guardian
- 発行日: 2025年4月19日
- URL: https://www.theguardian.com/technology/2025/apr/19/dont-ask-what-ai-can-do-for-us-ask-what-it-is-doing-to-us-are-chatgpt-and-co-harming-human-intelligence
要点
- 知能指数の低下傾向: 過去数十年にわたり上昇傾向にあったIQ(知能指数)が、近年、一部の国や地域で低下傾向(フリン効果の逆転)が見られます。
- AIと認知能力の関係: AI、特に生成AIへの依存が、人間の批判的思考力、記憶力、創造性といった認知スキルを低下させる可能性が研究で示唆されています。
- 批判的思考力の低下: AIが瞬時に答えを提示するため、自ら深く考え、情報の意味、影響、倫理、正確性を吟味する機会が失われがちです。
- 創造性への影響: AIはアイデア生成を助ける一方、全体としては多様性に欠けるアイデアを生み出す傾向があり、画期的な発想を阻害する可能性があります。
- 専門家の警鐘: 専門家は、AIが「何をしてくれるか」だけでなく、「私たちに何をしているか」を問い、人間固有の能力(批判的思考、直感など)を再訓練する必要性を訴えています。
詳細解説
知能は低下しているのか?フリン効果の逆転
人間の知能が低下しているという議論の根拠の一つに、「フリン効果」の逆転があります。フリン効果とは、20世紀を通じて世界的にIQテストの平均点が上昇し続けた現象を指します。これは遺伝的要因ではなく、教育水準の向上や栄養状態の改善といった環境要因によるものと考えられてきました。
しかし、近年、特に先進国においてこのフリン効果が鈍化、あるいは逆転する現象が見られています。例えば、イギリスでは1980年から2008年の間に14歳の平均IQが2ポイント以上低下したという研究結果があります。また、国際的な学力調査PISAでも、多くの地域で数学、読解力、科学のスコアが前例のないほど低下しています。
ただし、このIQ低下の要因をAIだけに求めるのは早計であると専門家は指摘します。栄養状態、教育、環境汚染、パンデミック、そしてテクノロジー利用の変化など、多くの要因が複雑に絡み合っているため、AIの影響だけを切り出して評価するのは困難です。
AIへの「認知オフロード」がもたらす懸念
私たちが日常的に行っている、スマートフォンで情報を検索したり、カーナビに頼ったりする行為は、「認知オフロード(Cognitive Offloading)」と呼ばれます。つまり、本来自分の脳で行うべき記憶や思考といった認知的作業を、外部のデバイスやツールに委ねることです。
生成AIの登場により、この認知オフロードはかつてないレベルで可能になりました。文章作成、プログラミング、芸術制作など、高度な知的作業もAIに任せられるようになったのです。これにより作業効率が向上するメリットがある一方で、特定の認知スキルを使う機会が減り、関連する脳の神経回路が衰えてしまうのではないか、という懸念が指摘されています。これは、運動をしなければ筋肉が衰えるのと同じ原理です。
批判的思考力の危機
特に懸念されているのが批判的思考力の低下です。AIは、私たちが疑問を投げかける前に、もっともらしい答えを瞬時に提示してくれます。これにより、情報源の信頼性を疑ったり、多角的な視点から物事を考えたり、情報の意味合いや倫理的な側面を深く考察したりする機会が失われがちになります。
スイスの研究者マイケル・ガーリッヒ氏が行った調査では、AIを頻繁に利用する人ほど批判的思考力が低いという相関関係が見られました。特に、AIへの依存度が高い若年層でその傾向が顕著でした。また、マイクロソフトとカーネギーメロン大学の研究でも、生成AIは作業効率を高める一方で、批判的思考を阻害し、長期的な過度の依存を招く可能性が示されています。ある研究参加者は、「AIに頼りすぎて、それなしでは特定の問題を解決する方法がわからないと思う」と述べています。
さらに、ソーシャルメディアのアルゴリズムも批判的思考の低下に拍車をかけています。短時間で注意を引くための断片的な情報が溢れ、深く考えることを促しません。AIによって生成された情報は、人間が作成したものよりも理解しやすく、かつ説得力のある偽情報である可能性も指摘されており(Science Advances誌の研究)、批判的に情報を見極める能力がますます重要になっています。
創造性は向上するか、画一化するか?
AIは、人間だけでは思いつかないようなアイデアを提示し、創造的なプロセスを支援する側面もあります。しかし、集団全体で見た場合、AIが生み出すアイデアは多様性に欠ける傾向があることも指摘されています。コーネル大学の心理学者ロバート・スタンバーグ氏は、「生成AIは既存のアイデアを再結合・再分類することはできるが、世界が直面する深刻な問題(気候変動、格差など)を解決するために必要な、既存の枠組みを打ち破るようなアイデアを生み出すかは不明だ」と述べています。
AIを能動的に使うか、受動的に使うかも、創造性への影響に関わる可能性があります。ドイツの研究者マルコ・ミュラー氏の研究では、若年層においてソーシャルメディア利用と創造性の高さに関連が見られましたが、これは彼らがアイデア共有や協働のために能動的に利用しているためではないかと推察されています。一方、受動的に情報を受け取るだけでは、創造的な刺激につながりにくいのかもしれません。
長期的な影響と今後の課題
AIへの依存は、批判的思考や創造性だけでなく、記憶力にも影響を与える可能性が指摘されています。また、脳の報酬系への影響も未知数です。自分で何かを発見したときの喜び(ひらめき)は、脳の報酬系を活性化させ、さらなる学習や創造性を促しますが、AIから得た情報では同様の効果が得られない可能性があります。
さらに、外国語学習が認知症の発症を遅らせる効果があることが知られていますが、AI翻訳アプリの普及により言語学習者が減少している現状も、長期的な脳の健康という観点から懸念されます。
スタンバーグ氏が警告するように、私たちは「AIが何をしてくれるか(what AI can do for us)」だけでなく、「AIが私たちに何をしているか(what it is doing to us)」を真剣に問う必要があります。
まとめ
本稿では、AI、特に生成AIの普及が人間の知的能力に与える潜在的なリスクについて解説しました。IQの低下傾向、批判的思考力や記憶力、創造性の減退といった懸念は、複数の研究や専門家によって指摘されています。
もちろん、AIは私たちの生産性を向上させ、様々な課題解決に貢献する大きな可能性を秘めたツールです。重要なのは、AIに思考を丸投げするのではなく、その限界や特性を理解した上で、賢く活用していくことです。 ガーリッヒ氏が言うように、「人間を再び人間らしく訓練する必要がある」のかもしれません。つまり、コンピュータにはまだできない批判的思考や直感といった能力を意識的に鍛え、AI時代における人間ならではの価値を高めていくことが求められます。教育現場をはじめ、社会全体でAIとの健全な向き合い方を学び、実践していくことが、私たちの未来にとって不可欠と言えるでしょう。