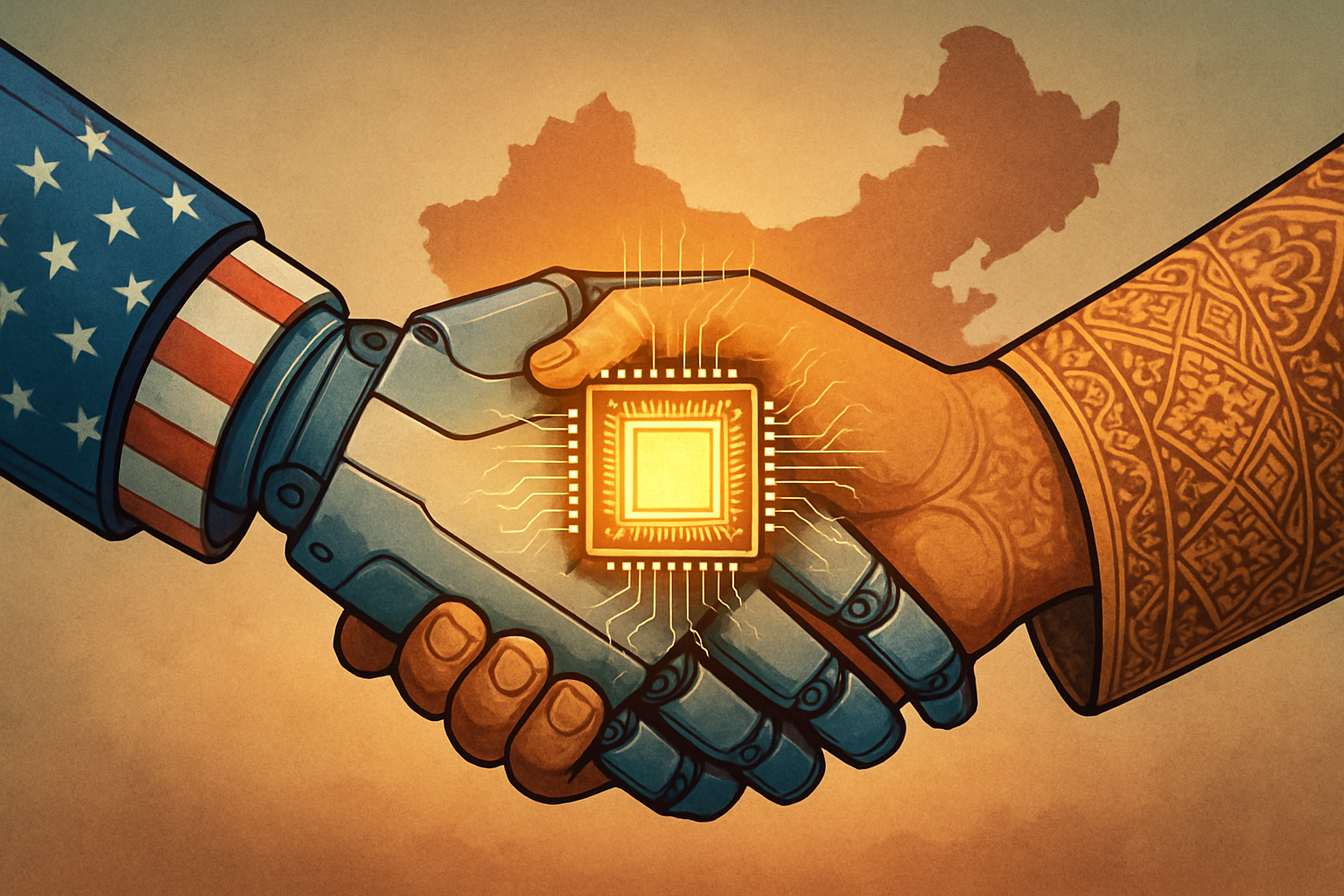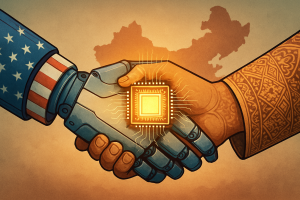はじめに
本稿では、米国のニュースサイトAxiosが2025年5月16日に報じた「Trump’s AI deals in Gulf stir China fears back home」という記事を基に、トランプ大統領(記事発行時点)が進める米国企業と湾岸諸国間の大規模な人工知能(AI)関連契約と、それに伴い米国内で高まる中国への先端技術流出や、米国のAI開発基盤が国外へ移転することへの懸念について、解説します。
引用元記事
- タイトル: Trump’s AI deals in Gulf stir China fears back home
- 発行元: Axios
- 発行日: 2025年5月16日
- URL: https://www.axios.com/2025/05/16/trump-ai-deals-gulf-chips-china-trade-policy

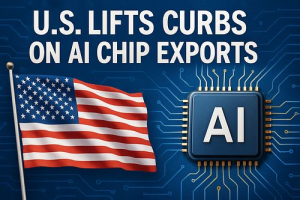
要点
- トランプ政権は、米国企業と湾岸諸国(特にサウジアラビア、アラブ首長国連邦(UAE))間で、数十億ドル規模のAI関連契約を積極的に推進している。これには、NvidiaやAMDといった大手半導体メーカーの高性能AIチップの供給や、Amazonなどによるデータセンター構築支援が含まれる。
- これらの動きに対し、米国内、特に議会や安全保障専門家の間では、湾岸諸国を経由して中国へ米国の最先端AI技術が流出するのではないかという強い懸念が表明されている。また、AI開発に不可欠な計算資源(データセンターなど)が米国外に集中することへの危惧も存在する。
- 背景には、トランプ政権が経済的利益や大型契約を重視する姿勢と、バイデン前政権時代に導入されたAIチップの輸出制限措置が、トランプ政権下で見直され、緩和される方向にあることがある。
- 一方で、米議会では超党派で、米国の高度AIチップが中国共産党のような敵対者の手に渡ることを防ぐための「チップセキュリティ法案(Chip Security Act)」が提出されるなど、技術流出への対策も模索されている。商務省も、関連取引には同省の承認が必要であるとのガイダンスを発表している。
- 湾岸諸国は、石油依存型経済からの脱却と経済多角化の一環としてAI分野への投資を強化しており、世界のAIハブとしての地位確立を目指している。米中両国との関係を維持しつつ、自国の国益を追求する戦略をとっている。
- 専門家は、これらの取引がもたらすリスクとして、短期的には湾岸諸国が中国への技術流出の「裏口」となる可能性、長期的にはAI開発の基盤となる計算インフラが米国外(特に湾岸諸国)に偏在し、米国のAI分野における主導権や管理能力が低下する可能性を指摘している。
詳細解説
トランプ政権下で加速する湾岸諸国とのAI協力
トランプ大統領は、米国企業と湾岸諸国との間で、AI分野における大型契約を次々と発表しています。これらは、米国のAI技術と湾岸諸国の豊富な資金力を結びつける動きとして注目されます。
具体的には、半導体大手のNvidiaが、サウジアラビアの政府系ファンドが支援する新しいAIインフラ企業Humainに対し、同国に建設される500メガワット規模のデータセンター向けに、18,000個の高度なAIチップを供給すると発表しました。Nvidiaの競合であるAMDもHumain社と100億ドル規模のパートナーシップを、Qualcommも同社と覚書を締結しています。さらに、AmazonとHumain社は、サウジアラビアに「AIゾーン」を開発するため、50億ドル以上を投資する計画です。これには、Amazon Web Services (AWS) のインフラやサーバーの提供、トレーニングプログラム、そしてサウジアラビア政府が利用するAIエージェントの開発などが含まれます。
また、報道によれば、トランプ政権はUAEに対して100万個以上の高度AIチップの輸出を認める取引を検討しているとされ、これを受けてOpenAIのような主要AI企業もUAEでのデータセンター開設を検討していると伝えられています。
ここで重要となる「AIチップ」とは、AIの計算処理、特に機械学習モデルの学習や推論を高速に実行するために特化した半導体のことです。現代のAI技術、例えば大規模言語モデル(LLM)などは、これらの高性能なチップなしには成り立ちません。特に「高度なAIチップ」は、その計算能力の高さから戦略物資と見なされており、国家間の技術覇権争いの焦点の一つとなっています。
そして、これらのAIチップを大量に搭載し、AIモデルの開発や運用を支える物理的な施設が「データセンター」です。データセンターは、現代のデジタル社会における心臓部とも言え、AI開発競争においては、その処理能力(計算資源の量と質)が国の競争力を左右します。
米国内に渦巻く懸念:中国への技術流出とAI覇権
こうした米国と湾岸諸国とのAI協力強化の動きは、米国内で深刻な懸念を引き起こしています。最大の懸念は、米国の最先端AI技術が、湾岸諸国を経由して中国に渡ってしまうのではないかという点です。
湾岸諸国、特にUAEは、経済の多角化を進める中で中国との経済的結びつきを強めており、軍事的な関係も維持していると指摘されています。このため、米国が輸出した高度なAIチップや関連技術が、最終的に中国の手に渡る「抜け穴」になる可能性が危惧されているのです。中国は国家戦略としてAI技術開発を強力に推進しており、米国の技術を獲得することは、その目標達成を加速させることにつながりかねません。
このような背景から、米下院の中国共産党に関する特別委員会は、米国の高度なAIチップが中国共産党のような敵対者の手に渡るのを阻止するための「チップセキュリティ法案(Chip Security Act)」を提出しました。この法案は、商務省に対し、高度AIチップの最終的な設置場所の検証を義務付け、チップメーカーには自社製品が規制対象企業や国に流用された場合の報告を義務付けるものです。
また、商務省の産業安全保障局(BIS)も、これらのAI関連取引が実行されるには同省の承認が必要であるとの新たなガイダンスを発表し、米国の敵対国が迂回ルートを使って米製チップにアクセスすることを防ぐ姿勢を示しています。
政策の揺り戻し:バイデン政権の規制とトランプ政権の方針転換
AIチップの輸出管理を巡っては、政権によって方針に揺れが見られます。バイデン前政権は、その任期末期に「AI拡散(AI diffusion)」ルールを導入し、サウジアラビアやUAEを含むほとんどの国への高性能AIチップの輸出に制限をかけました。これは、先端技術が軍事転用されたり、米国の安全保障を脅かす形で利用されたりすることを防ぐための措置でした。
しかし、NvidiaやMicrosoftといった大手テクノロジー企業は、この規制がイノベーションを阻害し、経済成長を妨げるとして強く反発しました。彼らは、グローバル市場での競争力維持のためには、より自由な技術取引が必要だと主張したのです。
記事によれば、トランプ政権はこのバイデン政権時代の輸出制限ルールを先週撤廃し、新たな政策を策定中であるものの、まだ完全には定まっていません。この政策の空白期間とも言えるタイミングで、大型契約が次々と発表されている状況です。ホワイトハウスのAI担当であるデビッド・サックス氏はサウジアラビアで、AIに関する「パートナーエコシステム」の構築を提唱し、チップに対する規制緩和を求める発言をしています。
こうした動きは、米国の経済的利益やビジネスの優位性を優先する立場と、国家安全保障を最優先し技術流出リスクを徹底的に管理しようとする立場との間で、政策のバランスが前者へと傾いていることを示唆しています。国家安全保障会議の報道官は「米国をAIのグローバルリーダーにしつつ、最先端技術が敵対者の手に渡らないようにする」という二つの目標は両立可能だと述べていますが、その具体的な道筋はまだ不透明です。
湾岸諸国の野心と地政学
一方、サウジアラビアやUAEといった湾岸諸国は、AI技術を国家の将来にとって極めて重要なものと位置づけています。長年依存してきた石油資源の価値が、世界の脱炭素化の流れの中で相対的に低下していくことを見据え、経済の多角化と新たな成長エンジンの獲得を急いでいます。AIはそのための切り札の一つであり、豊富なオイルマネーを背景に、AIインフラの整備や研究開発に巨額の投資を行っています。
ランド研究所のジミー・グッドリッチ氏は、「湾岸諸国はAIインフラとAIモデルの展開において、米国と中国に次ぐ世界第3極になるという大きな野心を持っている」と指摘しています。彼らは、AIが自国の経済的存続に不可欠であると認識しており、資金力と強い意志をもってこの分野に取り組んでいます。
地政学的に見ると、湾岸諸国は米国とも中国とも良好な関係を維持しようとする「全方位外交」あるいは「ヘッジ戦略」をとる傾向があります。中国との経済的・安全保障上の関係を断ち切ることも、米国との同盟関係を完全に反故にすることもない、というのが専門家の見方です。今回のAI関連の大型契約も、こうした湾岸諸国の戦略の一環と捉えることができます。
専門家が指摘する短期・長期のリスク
専門家は、米国と湾岸諸国間のAI協力が拡大することに伴うリスクを、短期的および長期的な視点から指摘しています。
短期的な懸念として最も大きいのは、やはり中国への技術流出リスクです。湾岸諸国が、意図的であるか否かにかかわらず、米国の高度なAIチップや関連技術が中国に渡るための「中継地点」となってしまう可能性が指摘されています。
より長期的な懸念としては、AI開発の基盤となる計算インフラが米国外、特に政府からの手厚い補助金が期待できる湾岸諸国に集中していく可能性です。そうなった場合、「コンピューティングの支配的なシェアを握る者がAIの未来を制する」という格言が現実味を帯びてきます。もし、AI開発に不可欠なサーバーラック、チップ、その他の計算コンポーネントが「数千マイル離れた砂漠地帯」に置かれるようになれば、米国がAI技術の進展や利用に対してどれだけのコントロールを維持できるのか、という問題が生じます。
グッドリッチ氏は、「我々はこの映画を以前にも見たことがある。何十年もの間、外国政府は我々の先端技術が海外に移転するよう補助金を出してきた。液晶パネル、半導体、太陽光発電、エネルギー分野など、これは未検証のトレンドではない」と警鐘を鳴らしています。つまり、過去にも米国の重要な技術が、他国の産業政策によって海外に流出し、結果として米国の競争力が削がれた事例があるという教訓です。
まとめ
本稿では、Axiosの記事を基に、トランプ政権下で進む米国と湾岸諸国とのAI分野における大型契約と、それに伴う米国内での中国への技術流出やAI開発基盤の海外移転といった懸念について解説しました。
これらの動きは、AI技術の発展と普及がもたらす経済的チャンスの追求と、それに伴う国家安全保障上のリスク管理という、二つの重要な側面が複雑に絡み合っている現代の国際情勢を象徴しています。特に、「高度なAIチップ」のような戦略的に重要な技術の管理や、AI開発の競争力を左右する「データセンター」といった計算インフラの立地戦略は、今後の世界のAI覇権の行方を占う上で極めて重要な要素となります。
湾岸諸国がAI分野での国際的なプレゼンスを高めようと積極的に動く中、米中間の技術覇権争いはさらに新たな局面を迎えています。日本としても、こうした国際的な技術動向や地政学的変化が、自国の経済安全保障や産業競争力、そしてAI技術戦略にどのような影響を与え得るのか、引き続き深く注視し、戦略的に対応していく必要があるでしょう。