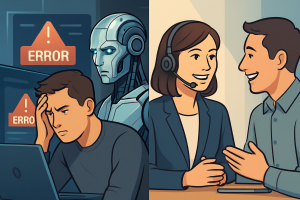はじめに
本稿では、近年多くの企業が注目する「AIファースト」戦略について、スウェーデンのフィンテック企業Klarna(クラーナ)と語学学習アプリDuolingo(デュオリンゴ)の事例を取り上げ、その実態と課題について解説します。AI技術の進化は目覚ましく、業務効率化やコスト削減への期待が高まる一方で、拙速な導入は思わぬ反発や問題を引き起こす可能性も秘めています。
引用元記事
- タイトル: Going ‘AI first’ appears to be backfiring on Klarna and Duolingo
- 発行元: Fast Company
- 発行日: 2025年5月12日
- URL: https://www.fastcompany.com/91332763/going-ai-first-appears-to-be-backfiring-on-klarna-and-duolingo
・本稿中の画像に関しては特に明示がない場合、引用元記事より引用しております。
・記載されている情報は、投稿日までに確認された内容となります。正確な情報に関しては、各種公式HPを参照するようお願い致します。
・内容に関してはあくまで執筆者の認識であり、誤っている場合があります。引用元記事を確認するようお願い致します。

要点
- Klarna及びDuolingoは、「AIファースト」戦略を推進し、AIによる従業員の代替を進めてきた企業である。
- Klarnaは、AI導入による顧客サポートの質の低下を認め、人間の担当者を再雇用する方針に転換した。
- Duolingoは、AI活用方針発表後、ソーシャルメディアでユーザーからの強い反発に直面している。
- 両社の事例は、AI導入によるコスト削減効果への期待と、消費者や従業員の懸念との間にギャップがあることを示唆している。
- AIが人間の仕事を完全に代替することへの抵抗感や、コントロールを失うことへの不安が、AI導入の課題となっている。
詳細解説
AIファースト戦略とは? KlarnaとDuolingoの挑戦
近年、多くの企業がデジタルトランスフォーメーション(DX)の中核としてAIの活用を掲げています。「AIファースト」戦略とは、事業運営のあらゆる側面において、AI技術の活用を最優先する考え方です。これにより、業務の自動化、効率化、コスト削減、そして新たな顧客体験の創出などが期待されます。
本稿で取り上げるKlarnaは、後払い決済サービスなどを提供するフィンテック企業です。同社CEOのセバスチャン・シェミオトコフスキ氏は、OpenAIの「お気に入りのモルモット」になることを宣言し、採用を凍結、可能な限り多くの従業員をAIシステムに置き換える方針を打ち出しました。実際に、AIが700人分の顧客サービスエージェントの業務をこなしていると発表していました。
一方、Duolingoは世界的に人気の語学学習アプリです。同社もAIファーストへの転換を発表し、AIが対応可能な業務委託契約を停止し、可能な限りの自動化を最大限に活用した上で初めて人員増を行うとしています。
Klarna:AI万能ではなかった
KlarnaはAIへの投資を継続しつつも、「人間の重要性」を再認識し始めているようです。シェミオトコフスキCEOは、顧客が常に人間の担当者と話せる選択肢を確保するために、大規模な採用活動を再開すると述べています。同氏は、「コストが(人員配置を決定する上で)あまりにも主要な評価要因であったため、結果として品質が低下してしまった」と、AI導入による顧客サポートの質の低下を認めています。今後は、学生や地方の人材も視野に入れ、人的サポートの質への投資を重視する方針です。これは、AIによる効率化だけでは、顧客満足度を維持・向上させることが難しい場合があることを示唆しています。
Duolingo:ユーザーからの厳しい視線とAIへの不信感
DuolingoのAIファースト戦略は比較的新しいものですが、発表直後からソーシャルメディア、特にTikTokで一般ユーザーからの激しい反発に直面しています。同社の投稿には、「AIではなく、本物の人間に会社を運営してほしい」「従業員を解雇してAIに置き換えるなんて」といった批判的なコメントが殺到しています。
ユーザーからは、「AIを使うなんてうんざりだ。言語学習は人間によって開拓されるべきだ」「この決定によって、Duolingoは環境、顧客、そして従業員を積極的に傷つけている」といった深刻な意見や、「AIファーストに進むなら、もうDuolingoは必要ない」としてアプリを削除したという報告も見られます。
これに対しDuolingo側は、「多くのフィードバックはDuolingoへの情熱から来るものであり感謝している」としつつ、「AIは学習の専門家に取って代わるものではなく、Duolingoをより良くするためのツールだ。AIで作成するものはすべて、学習デザインの専門家チームによって導かれている」と説明し、誤解があるとしています。しかし、ユーザーの不安や不信感を完全に払拭するには至っていないようです。
AI導入の背景と社会的な課題:効率性と人間性のジレンマ
企業がAI導入に積極的な背景には、コスト削減への大きな期待があります。世界経済フォーラム(WEF)の調査によると、雇用主の40%が労働力を削減し、自動化されたタスクをAI技術に委ねることを期待していると報告されています。Duolingoの株価は過去最高値を記録し、2025年の売上予測を引き上げるなど、経済的な成果を上げている側面もあります。
しかし、この経営層の熱意は、必ずしも消費者に共有されていません。Z世代の求職者の約半数は、AIが自身の大学教育の価値を低下させたと考えているとWEFに語っています。また、ハーバード大学の研究者は、AI技術が依然として人々にとって脅威であると指摘しています。ハーバード・ビジネス・スクールのジュリアン・デ・フレイタス助教授は、「人間は人生の早い段階から、目標を達成するために周囲の状況を管理しようと努める。そのため、状況に対するコントロールを低下させるように見えるイノベーションの採用には自然と消極的になる」と述べており、AIが人間のタスクを完全に奪う可能性は、深い懸念や心配を引き起こすとしています。
顧客対応業務やコンテンツ関連業務におけるAIの活用について
本記事で触れられているKlarnaやDuolingoの事例は、特に顧客対応業務やコンテンツ関連業務におけるAIの活用が焦点となっています。
- 顧客サービスにおけるAIチャットボットの導入と限界: KlarnaはAIを顧客サービスエージェントの代替として導入しましたが、最終的には「品質の低下」を認め、人間の担当者を再雇用する方針を示しました。これは、現在のAIチャットボットが、定型的な問い合わせには対応できても、複雑な問題解決や感情的なサポート、あるいは人間ならではの柔軟な対応が求められる場面では、まだ限界があることを示しています。自然言語処理(NLP)技術の進化は著しいものの、人間のコミュニケーション能力を完全に再現するには至っていません。
- 業務自動化と人間の役割の再定義: Duolingoは「AIが対応可能な業務委託契約を停止」すると述べており、これは翻訳、コンテンツ生成、あるいはデータ分析といった分野でのAI活用を示唆しています。AIによる自動化は効率化に貢献する一方で、これまで人間が担ってきた業務の価値や、人間の従業員が果たすべき役割について再考を迫られます。AIを「ツール」として活用し、人間の専門性をより高度な業務にシフトさせるという考え方が重要になりますが、その移行プロセスにおける従業員のスキル再教育や不安への対応が不可欠です。
- AIの品質管理と倫理的課題: AIが生成するコンテンツやAIが行う判断の品質をいかに担保するかは、依然として大きな課題です。Duolingoの事例でユーザーが懸念しているように、言語学習のようなニュアンスや文化的背景が重要な分野で、AIが不適切な内容を生成したり、学習効果を損なったりする可能性も考慮しなければなりません。また、AIの意思決定プロセスがブラックボックス化しやすいという問題もあり、透明性や説明責任の確保も技術的な課題の一つです。
まとめ
KlarnaとDuolingoの「AIファースト」戦略が直面している課題は、AI技術を社会に導入し、活用していく上での重要な教訓を示しています。AIは間違いなく私たちの働き方や生活に大きな変革をもたらす可能性を秘めていますが、その導入は慎重に進める必要があり、技術的な合理性だけでなく、人間の感情や社会的な受容性も十分に考慮する必要があります。
特に、顧客との接点や、人間の創造性・専門性が求められる分野においては、AIを万能と捉えるのではなく、人間を支援し、その能力を拡張するためのツールとして位置づけることが重要です。企業は、AI導入による短期的なコスト削減効果に目を向けるだけでなく、長期的な顧客との信頼関係や、従業員のエンゲージメント、そして社会全体の調和を視野に入れた戦略を策定する必要があるでしょう。
日本においても、これらの事例から学び、AIと人間が共存し、より豊かな社会を築いていくための議論を深めていくことが求められます。