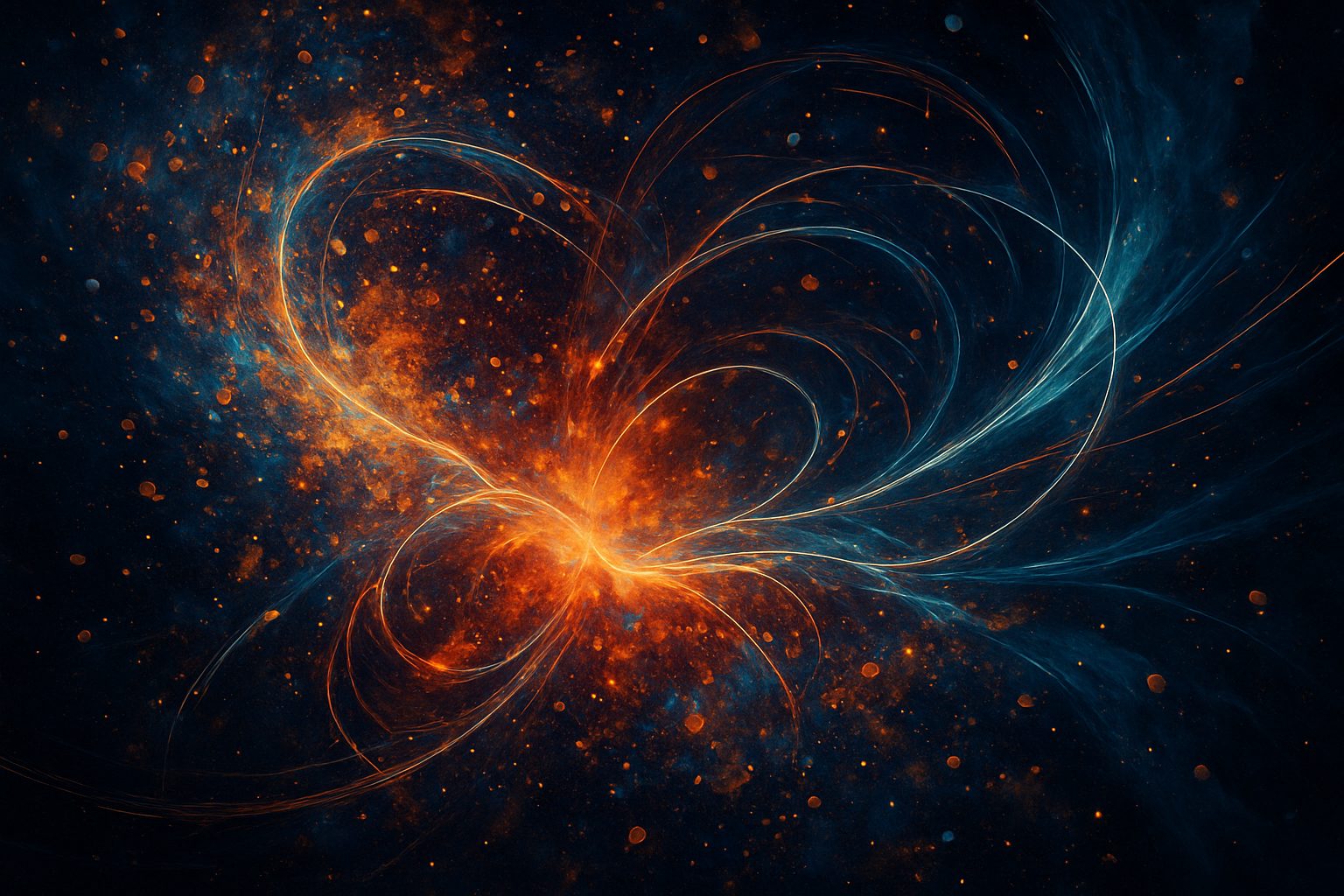はじめに
近年、急速な発展を遂げる人工知能(AI)は、私たちの社会に様々な変化をもたらしています。その影響は科学研究の分野にも及んでおり、AIは単なるデータ解析ツールに留まらず、未知の科学的法則を発見する能力を示し始めています。
本稿では、米国の科学雑誌『Popular Mechanics』に掲載された「An AI System Found a New Kind of Physics that Scientists Had Never Seen Before」という記事を元に、エモリー大学の研究チームがAIを用いて「ダストプラズマ」という特殊な物質内で起こる新しい物理現象を解明した研究について解説していきます。
参考記事
- タイトル: An AI System Found a New Kind of Physics that Scientists Had Never Seen Before
- 発行元: Popular Mechanics
- 発行日: 2025年8月7日
- URL: https://www.popularmechanics.com/science/a65606443/ai-discovery/
要点
- エモリー大学の研究チームが開発したAIが、プラズマの一種である「ダストプラズマ」における未知の物理法則を発見した。
- AIは、粒子間に働く力が互いに異なる「非相反的な力」の精密なモデルを初めて構築した。
- 従来、ダストプラズマ中の粒子の電荷はその大きさに比例すると考えられていたが、AIはそれが単純な比例関係ではなく、密度や温度にも影響されることを明らかにし、既存の理論を修正した。
- この研究は、AIが単なるデータ分析ツールではなく、科学的発見の主体となり得る可能性を示すものである。
詳細解説
物質の第4の状態「プラズマ」とは?
まず、この研究の舞台となる「プラズマ」についてご説明します。私たちは物質の状態として固体、液体、気体を学校で習いますが、プラズマはそれに続く「物質の第4の状態」と呼ばれています。気体を構成する原子や分子がさらに高いエネルギーによって、プラスの電気を帯びた「イオン」とマイナスの電気を帯びた「電子」に分かれた状態がプラズマです。
実は、宇宙に存在する観測可能な物質の99.9%以上はこのプラズマ状態にあるとされ、太陽や恒星、オーロラ、そして身近なところでは雷や蛍光灯の光もプラズマの一種です。
そして、本研究の対象である「ダストプラズマ」とは、このプラズマの中に、マイクロメートル(1000分の1ミリ)サイズの固体の微粒子(ダスト)が混在している状態を指します。ダストプラズマは、土星の環のような惑星リングや彗星の尾といった宇宙空間だけでなく、半導体の製造過程など、工業的な場面でも見られる非常に興味深い現象です。
AIが挑んだ「ダストプラズマ」の謎
ダストプラズマの中では、イオン、電子、そして電荷を帯びたダスト粒子が非常に複雑に相互作用しており、その全体の振る舞いを正確に予測することは極めて困難でした。そこで、エモリー大学の研究チームは、この複雑な現象を解明するために機械学習(ML)モデル、すなわちAIを活用しました。
発見1:粒子間に働く「非相反的な力」の解明
研究における最も重要な発見の一つが、「非相反的な力(non-reciprocal forces)」の精密なモデル化です。
通常、2つの物体の間で働く力は、作用・反作用の法則(AがBを押す力と、BがAを押す力は同じ大きさで逆向き)に従います。しかし、ダストプラズマのような複雑な環境では、この法則が単純には成り立ちません。
記事ではこの現象を「2隻のボートが互いの航跡(船が通った後にできる波)の影響を受ける」ことに例えています。自分の位置だけでなく、相手が作った環境(航跡)によって受ける力が変わるのです。
研究チームのAIは、この複雑な力の関係性について、「先行する粒子は後続の粒子を引きつけ、後続の粒子は常に先行する粒子を反発させる」という、これまで理論的には予想されていながらも、正確には記述されていなかった具体的な法則性を突き止めました。これは、ダストプラズマ内の粒子の動きをより正確に予測し、制御する上で重要な知見となります。
発見2:従来の物理理論の修正
さらに、このAIは、これまで信じられてきた理論的な思い込みを修正しました。
従来、ダストプラズマ中の粒子の電荷は、その粒子の大きさに単純に比例すると考えられてきました。しかし、AIがデータを解析した結果、大きな粒子ほど大きな電荷を帯びる傾向はあるものの、それは単純な比例関係ではないことが明らかになりました。粒子の電荷は、大きさだけでなく、周囲のプラズマの密度や温度、さらには他の粒子の大きさにも影響される、より複雑な関係性を持っていたのです。
「学習データなきAI」という挑戦
この研究の興味深い点は、AIの開発手法にもあります。通常、AIは「教師データ」と呼ばれる大量の正解データを学習することで性能を高めます。例えば、AIに猫の画像を100万枚見せれば、猫を正確に認識できるようになります。
しかし、「未知の物理法則を発見する」というタスクには、手本となる教師データが存在しません。そこで研究チームは、AIに物理学の基本的な制約を与えつつも、その範囲内で自由に新しいパターンや法則を探求できるような、特殊な構造を持つAIを設計しました。これにより、AIは既知の知識の枠を超え、新たな発見をすることができたのです。
まとめ
本稿では、AIがダストプラズマという複雑な系において、これまで知られていなかった物理法則を発見し、既存の理論を修正したエモリー大学の研究について解説しました。
この成果は、特定の物理現象の理解を深めただけでなく、AIが科学研究において果たす役割そのものを変える可能性を秘めています。AIはもはや、人間が設定した問題を解くためのツールに留まりません。自ら問いを立て、データを分析し、これまで誰も気づかなかった自然界の法則を「発見」する、科学者の新たなパートナーとなりつつあります。今後、物理学だけでなく、化学、生物学といった様々な分野で、AIによる科学的発見が加速していくことが期待されます。