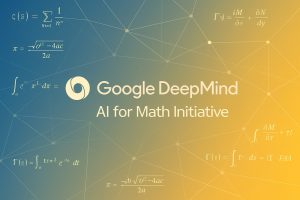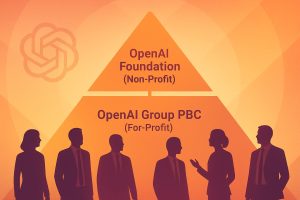はじめに
インターネットのトラフィックの約半分は「ボット」と呼ばれる自動化されたプログラムによって占められていると言われています。そして、AI技術の進化により、このボット問題はさらに深刻化しています。
本稿では、AIがインターネットのボット問題をどのように悪化させているのか、そして、この課題に最前線で取り組むスタートアップ企業「Persona」の挑戦について、Forbesの記事を元に解説します。
引用元記事
- タイトル: AI Is Making The Internet’s Bot Problem Worse. This $2 Billion Startup Is On The Front Lines
- 発行元: Forbes
- 発行日: 2025年4月30日
- URL: https://www.forbes.com/sites/rashishrivastava/2025/04/30/ai-is-making-the-internets-bot-problem-worse-this-2-billion-startup-is-on-the-front-lines/
要点
- インターネット上のボットによるトラフィックは既に約50%を占め、AIエージェントの普及により2030年までに90%に達する可能性があると予測されています。
- AIは、従来のCAPTCHA(画像認証など)のようなボット検出技術を容易に突破し、ディープフェイク(AIによる偽の顔や声の生成)や偽造IDの作成を容易にし、オンライン詐欺のリスクを高めています。
- サンフランシスコを拠点とするスタートアップ「Persona」は、OpenAI、LinkedIn、Redditなどの企業に対し、高度な本人確認ソリューションを提供し、2億ドルの新たな資金調達に成功、評価額は20億ドルに達しました。
- Personaは、政府発行IDの写真、セルフィー動画(ライブネステスト)、パスポートのNFCチップスキャン、利用者のネットワークやデバイス操作パターンなどのリスクシグナル分析を組み合わせた、多層的かつカスタマイズ可能な本人確認プロセスを提供しています。
- 今後の課題は、単にボットか人間かを見分けるだけでなく、AIエージェントを含むあらゆるオンライン活動の背後にある「意図」と「本人性」を検証することへとシフトしています。
詳細解説
深刻化するインターネット上のボット問題
私たちが日常的に利用するインターネットですが、その通信の大部分は人間ではなく、ボットによって占められています。ボットとは、特定のタスクを自動的に実行するプログラムのことです。商品を購入したり、アカウントを作成したり、情報を収集したりと、様々な目的で利用されます。
ボットには、ウェブサイトの情報を収集する検索エンジンのクローラーのような「良いボット」もいますが、問題となるのは「悪いボット」です。例えば、限定商品を買い占めて転売する、不正にアカウントを作成・乗っ取りする、サービスのサーバーに負荷をかけてダウンさせる、といった悪意のある活動を行います。
記事によると、現在のインターネットトラフィックの約半分は既にボットによるものですが、人々がAIエージェント(AIを利用して日常的なタスクを代行するプログラム)を使い始めると、この割合は2030年までに90%に急増する可能性があると指摘されています。これにより、企業は不正利用や詐欺のリスクにさらに晒されることになります。
AIがボット検出を困難にする理由
従来、ウェブサイトはボットと人間を区別するためにCAPTCHA(歪んだ文字を読ませたり、特定の画像を選ばせたりする認証)のような技術を利用してきました。しかし、近年のAI技術の進化により、これらの技術は容易に突破されるようになっています。AIは人間のように画像を認識し、文字を読み取ることができるためです。
さらにAIは、ディープフェイク技術を用いて本物そっくりの偽の顔写真や動画、音声を生成したり、偽の身分証明書を作成したりすることを可能にしました。これにより、オンライン上でのなりすましや詐欺がより巧妙かつ容易になっています。
Persona社の革新的な本人確認ソリューション
このような状況下で注目を集めているのが、本人確認プラットフォームを提供するスタートアップ企業「Persona」です。同社は、OpenAI(ChatGPTの開発元)、LinkedIn、Etsy、Reddit、DoorDash、Robinhoodといった名だたる企業を含む3,000社にサービスを提供しています。最近では、2億ドルの資金調達に成功し、企業評価額は20億ドル(約3000億円 ※1ドル150円換算)に達しています。
Personaの強みは、単一の方法に頼るのではなく、複数の検証方法を組み合わせ、利用シーンやリスクレベルに応じてカスタマイズされた確認プロセス(フロー)を提供できる点にあります。具体的には、以下のような技術を組み合わせています。
- 政府発行IDの検証: 運転免許証やパスポートなどの写真データをアップロードさせ、その真正性を検証します。
- セルフィーとライブネス(生体)テスト: 利用者にセルフィー写真や、顔を動かしたり瞬きしたりする短い動画を撮影させ、提出されたIDの人物と同一であり、かつ「生きている」人間であることを確認します(ライブネステスト)。これにより、写真やディープフェイクによるなりすましを防ぎます。
- NFCチップスキャン: パスポートに埋め込まれているNFCチップをスマートフォンでスキャンさせ、より確実な本人確認を行います。
- リスクシグナルの分析: 機械学習モデルを用いて、利用者が使用しているネットワーク(VPNなど)、IDに記載された場所からの距離、デバイスの操作方法(コピー&ペーストの多用、入力間の不自然な間、機械的な操作リズムなど)、オンライン上の活動履歴といった様々なリスクシグナルを検知し、不審な点を洗い出します。
例えば、フードデリバリーアプリでアルコールを注文する際の年齢確認と、融資を申し込む際の本人確認では、求められる検証の厳格さが異なります。Personaは、こうしたユースケースごとに最適な確認フローを構築し、利用者にとってはスムーズで、企業にとっては安全な認証を実現します。
今後の展望:AIエージェントとポータブルなデジタルID
PersonaのCEOであるリック・ソング氏は、「ボットか否かという区別は、もはや意味をなさなくなるかもしれない。真の問題は、AIの背後にいるのは誰で、その意図は何かということだ」と述べています。今後は、人間だけでなく、AIエージェントの登録や、その利用目的の正当性を検証する必要が出てくるかもしれません。
さらにPersonaは、個人のオンライン活動(食事の注文、SNSの閲覧など)の履歴から、改ざん困難で持ち運び可能な個人のアイデンティティプロファイル(self-sovereign, personally-owned portable identity)を構築するという構想を持っています。これにより、様々なサイトで迅速かつ安全に本人確認を行えるようになる未来を目指しています。プライバシーとのトレードオフはありますが、オンラインでの情報開示が増える現代において、このような安全なデジタルIDの必要性は高まっていくと考えられます。
まとめ
AIの進化は、インターネット上のボット問題を新たな次元へと引き上げ、オンラインでの本人確認のあり方に変革を迫っています。従来のCAPTCHAのような単純な手法は通用しなくなりつつあり、ディープフェイクなどの脅威も増大しています。
このような課題に対し、Persona社は、多層的な検証技術とリスク分析、そしてユースケースに応じたカスタマイズを組み合わせることで、より高度で信頼性の高い本人確認ソリューションを提供しています。彼らの取り組みは、単に不正を防ぐだけでなく、AIエージェントが普及する未来において、オンライン上の活動の「意図」と「本人性」をいかに担保していくかという、より本質的な問いへの挑戦と言えるでしょう。安全で信頼できるデジタル社会の実現に向けた、重要な一歩となることが期待されます。