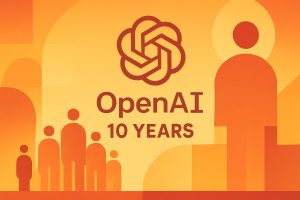はじめに
本稿では、テクノロジーが私たちの生活や文化に与える影響、特に人工知能(AI)と創造性の関係について、一つの事例を通して考察します。長年にわたり病気と闘う子供たちのためにオーダーメイドの曲を制作してきた非営利団体が、その活動をさらに広げるためにAI音楽生成ツールを導入した試みについて、導入によるメリット、デメリットの両面が見えてきます。
参考記事
- タイトル: Songs of Love writes personalized music for kids — but can AI carry the tune?
- 著者: Chloe Veltman
- 発行元: NPR (National Public Radio)
- 発行日: 2025年8月1日
- URL: https://www.npr.org/2025/08/01/nx-s1-5480186/songs-of-love-music-ai-seniors-dementia
要点
- 非営利団体「Songs of Love Foundation」は、重い病気を持つ子供たちのため、約30年間で46,000曲以上のパーソナライズされた楽曲を無償で提供してきた団体である。
- この団体は、新たに認知症の高齢者へもサービスを拡大するため、AI音楽生成プラットフォーム「Suno」の技術を導入した。
- AI導入の主な理由は、高齢者が慣れ親しんだ古い時代の音楽(ビッグバンド、ドゥーワップなど)を authentically(本物らしく)制作できる作曲家を見つけることが困難であったためである。
- AIの活用により、作曲家は自身の録音を本格的な楽曲に仕上げたり、特定の楽器パートを生成したりと、制作プロセスを効率化できる。
- 一方で、AIの利用は、作曲家と楽曲を受け取る人との間の人間的なつながりを損なうのではないかという懸念を生んでいる。
- AIの学習データに関する著作権問題や、AI導入に伴い作曲家への報酬が停止されボランティア制に移行したことなど、倫理的・経済的な課題も存在する。
- 関係者の間では、AIを「創造性を助けるツール」と肯定的に捉える声と、「プロセスを無菌化し、人間味を失わせる」と懐疑的に見る声があり、意見が分かれている。
詳細解説
「Songs of Love Foundation」とは? – 心を癒すパーソナルソング
まず、本稿の中心となる「Songs of Love Foundation」について説明します。この団体は、深刻な病気や障害と闘う子供たちに、その子だけのために作られたオリジナルの歌をプレゼントするという活動を、1996年から続けている米国の非営利団体です。
依頼があると、親や保護者は子供の趣味、好きな食べ物、家族や友人の名前、ペットの名前といった個人的な情報を団体に提供します。その情報に基づき、団体に登録されているプロの作曲家が、その子の好きな音楽ジャンルで、世界に一つだけの歌を制作します。記事で紹介されているローガン・ベッカー君は、この歌を受け取ったことで「自分は一人じゃないんだ、社会に受け入れられているんだと感じる」と語っています。
音楽には古くから人を癒す効果があるとされていますが、重要なのは、この団体の活動が「音楽療法」とは異なる点です。音楽療法は、資格を持つ専門家が心理学や医学などの専門知識を用いて行う医療行為です。一方で、Songs of Loveの活動は、音楽を通じて子供たちの心を元気づけ、「自分という存在が認められている」という肯定感を与えることに大きな価値があります。ニューヨーク大学の音楽療法プログラムの責任者であるケネス・アイゲン氏は、自分のためだけに作られた歌がもたらす普遍的な感覚は、大きな慰めになり得ると指摘しています。
なぜAIが必要だったのか? – 新たな挑戦と課題
長年、人間の作曲家による活動を続けてきたSongs of Loveが、なぜAIの導入に踏み切ったのでしょうか。その背景には、創設者ジョン・ベルツァー氏の個人的な経験と、活動拡大に伴う現実的な壁がありました。
ベルツァー氏の母親はアルツハイマー病を患っており、彼はその経験から、活動の対象を認知症に苦しむ高齢者にも広げたいと考えるようになりました。しかし、ここで問題が生じます。高齢者、特に認知症の方々にとって心地よい音楽は、彼らが若かりし頃に聴いたビッグバンドやドゥーワップ、スウィングといった、今では演奏できる人が少なくなったジャンルの音楽です。ベルツァー氏は「そうした楽曲を本物らしく制作できる作曲家を十分に見つけることは不可能だった」と語ります。
この課題を解決するために彼らが提携したのが、AI音楽生成プラットフォームの「Suno」です。Sunoは、テキストで指示するだけで楽曲やボーカル、楽器パートを生成できるサービスで、この技術を使えば、特定の時代の音楽スタイルを再現することが容易になります。Suno社はこの趣旨に賛同し、Songs of Loveの作曲家たちにツールを無償で提供することを決定しました。
AIは作曲家をどう変えるか? – 現場からの声
AIの導入は、作曲の現場に何をもたらしたのでしょうか。関係者の意見は、期待と懸念の両面に分かれています。
長年この団体で活動してきた作曲家のトーマス・ジョーンズ氏は、AIの利用に非常に肯定的です。彼はSunoのツールを頻繁に利用しており、「AIは自分を表現するためのもう一つの方法にすぎない。まるでクレヨンの箱のようなものだ」と語ります。彼にとってAIは、創造性を補助し、表現の幅を広げるための便利なツールなのです。
しかし、すべての作曲家がそう考えているわけではありません。かつてこの団体で約600曲もの歌を作曲したロス・オレンシュタイン氏は、AIの利用に強い懸念を示しています。彼は「プロセスが無菌化されてしまう。人間味が失われる」と述べ、AIが介在することで、作り手と受け手の間にあったはずの温かい感情のやり取りが損なわれると危惧しています。
さらに、この変化は作曲家の労働環境にも影響を及ぼしています。これまで団体は作曲家に少額の謝礼を支払っていましたが、AI導入によるサービス拡大に伴い、その支払いは停止され、作曲活動は完全にボランティアとなりました。効率化の裏で、人間の専門家の仕事が経済的に評価されなくなるという、AI時代に共通する課題がここにも見て取れます。
人間とAIの協業の未来 – 議論のポイント
この事例は、AIと人間の関係性について、さらに広い論点を提示しています。
一つは、「人間的なつながり」の価値です。Songs of Loveと同様に病気の子供たちへの楽曲提供を行う別の団体「Hear Your Song」は、AIの導入に慎重な姿勢を示しています。その理由は、彼らのプログラムの価値は「人間関係の深さにある」からだと言います。子供の幸福感や自己表現にとって最も重要なのは、AIを介さない人間同士の直接的なつながりである、という考え方です。
もう一つは、著作権の問題です。Sunoを含む多くのAI企業は、既存のアーティストの楽曲を許可なく学習データとして使用したとして、現在複数の訴訟を抱えています。善意の活動であっても、その基盤となる技術が法的にグレーな領域にあるという事実は、無視できない問題です。
音楽療法士のサンギータ・スワミー氏は、「ソングライターと患者の間には、エネルギー的、あるいは精神的な関係があります。彼らはつながろうとしているのです」と述べ、AIが生成した曲にはその「つながりの要素」が欠けていると感じると指摘しています。
まとめ
本稿で紹介した「Songs of Love Foundation」の事例は、AI技術が社会貢献活動に新たな可能性をもたらす一方で、人間性の本質、創造性の価値、そして人と人とのつながりの意味を私たちに深く問いかけています。
AIによって、これまで手が届かなかった人々にもサービスを届けられるようになり、表現の幅も広がりました。これは紛れもなく、テクノロジーがもたらした大きな進歩です。しかしその一方で、効率化を追求するあまり、プロセスから「人間」が排除され、本来最も大切だったはずの温かみや精神的な交流が失われてしまう危険性もはらんでいます。
AIはあくまでツールであり、それ自体に善悪はありません。重要なのは、私たちがそのツールをどのように使い、何を大切にするかです。効率性や規模の拡大と、人間的な温かみや深いつながりをいかにして両立させるか。この問いに対する答えを見つけていくことが、AIと共存する未来を築く上で、私たち全員に課せられた重要な課題と言えるでしょう。