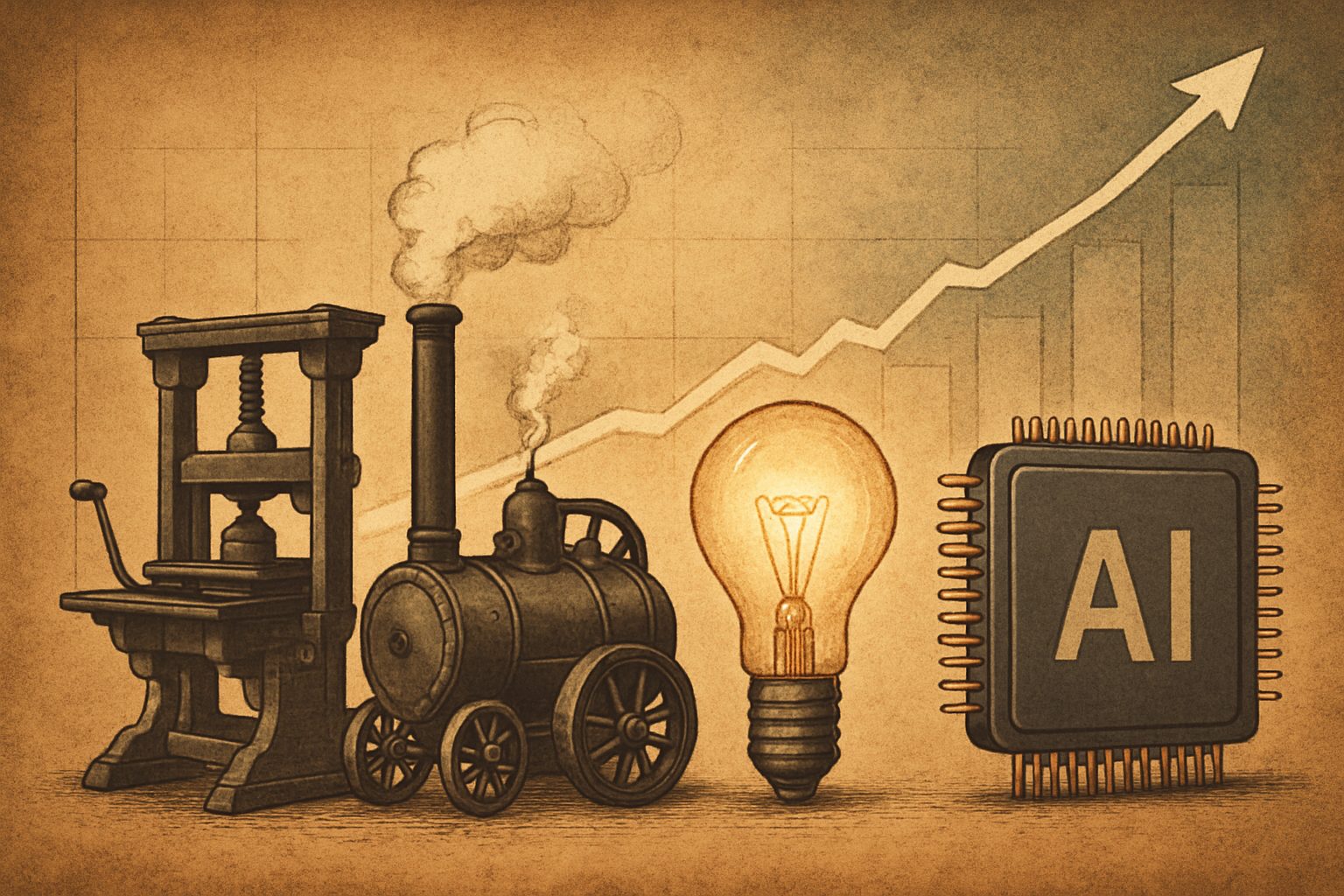はじめに
本稿では、2025年7月17日に米国連邦準備制度理事会(FRB)の理事であるリサ・D・クック氏が行った講演「AI: A Fed Policymaker’s View」をもとに、人工知能(AI)が経済、特にFRBの使命である「最大雇用」と「物価安定」にどのような影響を与えるのかを解説します。
参考記事
- タイトル: AI: A Fed Policymaker’s View
- 著者: Governor Lisa D. Cook
- 発行元: Board of Governors of the Federal Reserve System
- 発行日: 2025年7月17日
- URL: https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/cook20250717a.htm
要点
- AIは印刷機や電力に匹敵する「汎用技術(General-Purpose Technology)」であり、経済の歴史的な転換点にある。
- AIは、生産性を飛躍的に向上させることでインフレ圧力を抑制する可能性がある一方、導入のための大規模な投資が短期的に物価を押し上げる可能性も持つ。
- 労働市場において、AIは一部の仕事を代替する一方で、新たな仕事やタスクを創出し、労働市場全体を再編する力がある。
- FRBは、AIがもたらすこれらの複雑な影響を慎重に分析し、金融政策を運営していく必要がある。
- AIの導入と社会実装を成功させるためには、人間が主導権を握る「責任あるAI活用」(強力なガバナンス、教育、実験など)が不可欠である。
詳細解説
AIは現代の「電力」:汎用技術(GPT)としてのインパクト
クック理事は講演の冒頭で、AIを「汎用技術(General-Purpose Technology, GPT)」であると位置付けています。これは非常に重要な指摘です。
汎用技術とは、特定の産業だけでなく、社会や経済のあらゆる側面に影響を及ぼし、新たなイノベーションを次々と誘発する基盤的な技術を指します。歴史を振り返ると、蒸気機関、電力、インターネットなどがその代表例です。これらが登場したことで、私たちの働き方、生活、そして経済の形そのものが根本から変わりました。
クック理事は、AIがこれらと同じレベルのインパクトを持つと考えているのです。つまり、AIは単に特定の業務を効率化するツールではなく、経済全体の生産性を向上させ、新しい産業やサービスを生み出す「エンジン」になる可能性を秘めているということです。
FRBの二大責務への影響:物価と雇用の未来はどうなるか
FRBには、「最大雇用」と「物価の安定」という2つの大きな使命(デュアル・マンデート)があります。AIの登場は、この両方に大きな影響を与えると予測されています。
1. 物価の安定(インフレとの関係)
AIが物価に与える影響は、二つの側面から考える必要があります。
- インフレ抑制効果(ポジティブな側面): AIは、企業の業務プロセスを効率化し、コストを削減することで生産性を向上させます。生産性が上がれば、企業は同じ労働力でより多くの製品やサービスを生み出せるようになり、価格上昇の圧力を和らげることができます。クック理事は、この生産性向上によるディスインフレ(インフレ抑制)効果が、長期的に物価を安定させる力になる可能性を指摘しています。
- インフレ加速リスク(短期的な懸念): 一方で、AI技術を経済全体で導入するためには、膨大な投資が必要になります。例えば、高性能な半導体チップ、データセンターの建設、ソフトウェア開発などへの投資が急増すれば、それが総需要を刺激し、短期的に物価を押し上げる可能性があります。
このように、AIは物価に対して相反する力を同時に及ぼす可能性があり、金融政策のかじ取りはより一層難しくなります。
2. 最大雇用(仕事の未来)
AIが仕事を奪うのではないか、という懸念を多くの人が抱いています。クック理事も、過去の技術革新と同様に、一部の仕事がAIに代替される可能性は認識しています。
しかし、同時に新しい仕事やタスクが生まれることも強調しています。AIは、人間の判断が必要な知的作業を「代替」するだけでなく、「拡張」する能力を持っています。例えば、医師がAIの助けを借りて診断精度を高めたり、研究者がAIを使って膨大なデータから新しい発見をしたりするなど、AIを使いこなすことで付加価値を生み出す新しい役割が生まれると考えられます。
重要なのは、この労働市場の移行期に生じる痛みを認識しつつも、社会全体として新しいスキルの習得や再教育をどう進めていくか、という点です。
責任あるAI導入の重要性
クック理事は、AIの大きな可能性を認めつつも、その導入には慎重なアプローチが必要だと強調し、「責任あるAI導入」のための4つの原則を提唱しています。
- 強力なガバナンスとリスク管理: AIの判断を鵜呑みにするのではなく、常に「人間がループの中にいる(humans are in the loop)」という考え方が中心であるべきです。最終的な意思決定の責任は人間が負うという体制を築き、プライバシーやサイバーセキュリティのリスクを管理することが不可欠です。
- スタッフの教育と訓練: 従業員がAIを効果的に活用できるよう、継続的な教育と訓練が重要になります。
- エンパワーメント: 組織内のチームが、管理された環境でAIを実際に試せるように後押しすることが、実践的な知見を蓄積する上で役立ちます。
- 実験: 厳格な基準を満たさないプロジェクトは中止する能力を維持しつつ、新しい試みを奨励するオープンな文化を育むことが大切です。
FRB自身の取り組みとAI導入の課題
FRBは、AIを評論するだけでなく、自らの組織内でも経済分析や調査のために積極的に活用し始めています。例えば、金融政策委員会の議事録の読解、企業の決算発表からAI関連の研究開発動向の測定、金融危機の予測などにAIや機械学習の技術を応用する研究が進められています。
こうした自らの経験を通して、なぜAIの導入が社会全体で爆発的に進まないのか、その理由も見えてきたとクック理事は語ります。それは、①新しい技術を使いこなすための人材育成には時間がかかること、②組織内で成功体験や知見が広まるのに時間がかかること、③技術の進歩が速すぎて、どの技術を導入すべきか見極めが難しいこと、などが挙げられます。これは、多くの日本企業が直面している課題とも共通するでしょう。
まとめ
本稿では、FRBのリサ・クック理事の講演を基に、AIが経済と金融政策に与える多角的な影響について解説しました。
クック理事の姿勢は「慎重な楽観主義(cautiously optimistic)」と要約できます。AIが生産性を向上させ、私たちの生活を豊かにする大きな可能性を秘めていることを認めつつも、その過程で生じる労働市場の変化や短期的なインフレリスク、そして技術を正しく使うための倫理的な課題など、乗り越えるべき壁があることを冷静に分析しています。
AIという巨大な変化の波は、もはや避けられません。私たち一人ひとりが、この新しい技術とどう向き合い、自らの仕事や社会をどう変えていくべきかを考える上で、中央銀行の政策担当者が抱く視点は、非常に重要な示唆を与えてくれるのではないでしょうか。