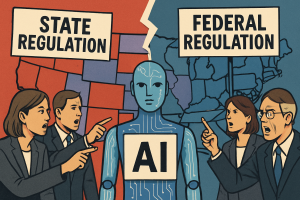はじめに
近年、私たちの生活のあらゆる場面で人工知能(AI)技術の活用が急速に進んでいます。その一方で、AI技術の進化に伴うリスクや倫理的な課題も顕在化しており、各国で規制のあり方が議論されています。
本稿では、米国におけるAI規制の新たな動きとして、連邦議会下院の委員会で審議されている「AIに関する州法の10年間執行停止措置」について、その背景や影響についてTech Policy Pressの記事「US House Committee Advances 10-Year Moratorium on State AI Regulation」をもとに詳しく解説します。
引用元記事
- タイトル: US House Committee Advances 10-Year Moratorium on State AI Regulation
- 発行元: Tech Policy Press
- 発行日: 2025年5月14日
- URL: https://www.techpolicy.press/us-house-committee-advances-10-year-moratorium-on-state-ai-regulation/
要点
- 米国下院エネルギー・商業委員会において、AIに関連する州レベルの法律や規制の執行を、法案成立から10年間停止する案が共和党主導で進められている。
- この提案の背景には、州ごとに異なる規制がAIの技術革新やビジネス展開の妨げになることを懸念し、連邦レベルで統一的なアプローチを確立すべきという考え方がある。
- 一方で、この措置に対しては、消費者保護やAIによる潜在的な危害への対応が遅れるとの強い批判も出ている。
- 過去のインターネット税のモラトリアム(一時停止措置)が、今回の提案の論拠の一つとして挙げられている。
詳細解説
10年間モラトリアム提案の背景と内容
米国では、連邦政府と州政府がそれぞれ法律を制定する権限を持っています。AI技術が急速に発展する中で、カリフォルニア州をはじめとするいくつかの州では、AIがもたらすリスク(例えば、ディープフェイクによる偽情報拡散、アルゴリズムによる差別、AIコンパニオンの倫理的問題など)に対応するための独自の法律や規制を導入、または検討しています。
しかし、2025年3月13日(記事本文中の日付、法案提出は5月の日曜)、下院エネルギー・商業委員会の共和党議員らは、予算調整法案の一部として、これらの州レベルのAI規制を10年間停止するという大胆な提案を盛り込みました。この法案の「人工知能と情報技術の近代化イニシアチブ」と題されたセクション(第43201条)では、連邦政府のITシステムを商用AI技術で近代化し、業務効率やサービス提供の向上、自動化、サイバーセキュリティの強化を義務付ける内容が含まれています。そして、その(c)項で次のように規定されています。
…いかなる州またはその下部組織も、本法の制定日から始まる10年間において、人工知能モデル、人工知能システム、または自動意思決定システムを規制するいかなる法律または規制も執行してはならない。
この提案を支持する共和党のジェイ・オバノルテ議員は、「AIが規制されるべきでないと考える者はいない」としながらも、それは州ではなく連邦議会の役割であるべきだと主張しています。「議会は行動を共にし、連邦規制当局を包括的なAIの枠組みでバックアップするためのAI法案を制定する必要がある」と述べ、「誰もこれが10年も続くことを望んでいない」とも付け加えています。つまり、この10年間は、連邦レベルで統一された規制を整備するための「学習期間」と位置づけられている側面があるようです。
イノベーション促進か、消費者保護の後退か
このモラトリアム案の支持者は、かつて1998年に制定された「インターネット税自由法(Internet Tax Freedom Act)」の成功例を引き合いに出しています。この法律は、州や地方政府によるインターネットアクセスへの課税を禁止するもので、電子商取引の黎明期においてその成長を大きく後押ししたと評価されています。上院商業・科学・運輸委員会の委員長であるテッド・クルーズ上院議員(共和党)は、同様の措置がAIのイノベーションを促進するために必要であると示唆しています。OpenAIのサム・アルトマンCEOやマイクロソフトのブラッド・スミス社長といった大手IT企業の幹部も、連邦レベルでの統一的かつ「ライトタッチ」なアプローチに賛同する意向を示しています。
この考え方の根底には、各州がバラバラに規制を設けることで、AI開発者や企業が複雑な規制の網の目に対応しきれなくなり、技術革新の足かせになるという懸念があります。また、連邦政府自身がAIシステムを導入・近代化する上でも、州ごとの規制の乱立は障害になり得るとの主張もなされています。
一方で、この提案には多くの批判の声が上がっています。民主党のドリス・マツイ議員は、このモラトリアムを「アメリカの消費者に対する平手打ち」と厳しく非難し、連邦レベルでは明確な保護がない様々な危害に対してカリフォルニア州が制定してきた法律の重要性を指摘しました。また、キャシー・キャスター議員(民主党)は、この措置を「富裕層への減税策に紛れ込ませた衝撃的なサプライズ」と呼び、Encode AI、Common Sense Media、Consumer Reports、Issue Oneといった市民団体からの反対意見書を読み上げました。
これらの批判者は、AI技術が急速に進化し、社会への影響が拡大する中で、10年間もの間、州レベルでの新たな規制が一切できなくなることは、ディープフェイク、選挙への偽情報工作、AIによる差別といった喫緊の課題への対応を著しく遅らせ、消費者を危険に晒すことになると警鐘を鳴らしています。特に、ソーシャルメディアに対する規制が遅れたことの教訓から、AIのように急速に進化する技術に対しては、より迅速な対応が必要であるとの意見が強調されています。
既存の法律は適用されるのか?
このモラトリアム案の提唱者の一人であるRストリート研究所のアダム・ティエラー氏は、この措置がAI技術開発者を野放しにすることを意味するわけではないと主張しています。彼によれば、モラトリアムはあくまで「新たな」州の規制を対象とするものであり、既存の様々な法律や規制(不正・欺瞞的行為防止法、公民権法、製品リコール権限、製造物責任法、裁判所ベースのコモンロー上の救済策、その他多様な消費者保護法など)は、AIによって生じうる危害に対しても引き続き適用可能であるとしています。
しかし、AIという新たな技術が生み出す特有のリスクに対して、既存の法制度だけで十分に対応できるのかという点については、依然として議論の余地があるでしょう。
今後の見通しと日本への影響
この法案は、下院本会議での採決を経て上院に送られますが、上院では「バード・ルール」と呼ばれる手続き上の仕組みにより、法案の趣旨と無関係とみなされる条項が削除される可能性があります。モラトリアム条項がこのバード・ルールによって異議を申し立てられる可能性も指摘されていますが、下院共和党はこれを回避するための論理構成を準備しているようです。具体的には、州ごとの複雑で相違のあるAI法が乱立することが、商務省によるAIシステム調達を妨げるため、モラトリアムが必要だという主張です。
仮にこのモラトリアムが成立した場合、AI法をすでに制定している州の司法長官などから法的な異議申し立てがなされる可能性もありますが、その成否は不透明です。
日本への影響という観点では、まず、米国におけるAI規制の動向は、世界のAIガバナンスの潮流に大きな影響を与えるため、日本政府の政策決定においても重要な参考情報となります。もし米国で連邦レベルの統一的な規制の枠組み作りが進むのであれば、日本もそれに整合性を取る形で国内法整備を進める動きが加速するかもしれません。
また、日本のAI関連企業が米国市場で事業を展開する際には、このモラトリアムの行方が事業戦略に影響を与える可能性があります。州ごとの規制対応の複雑さが一時的に緩和されるかもしれませんが、10年後には新たな連邦レベルの規制、あるいは再び州レベルの規制が動き出す可能性も視野に入れておく必要があります。
さらに、今回の議論は、イノベーション促進とリスク管理のバランスをどう取るかという、AIガバナンスにおける普遍的な課題を改めて浮き彫りにしています。日本においても、AI技術の恩恵を最大限に享受しつつ、その潜在的なリスクから国民を保護するための適切なルール作りが求められており、米国の議論から学ぶべき点は多いでしょう。特に、AI技術の進展の速さを考慮すると、10年という期間が適切なのか、より柔軟な見直し条項が必要ではないか、といった点も日本で議論する際の参考になるかもしれません。
まとめ
今回ご紹介した米国下院委員会における「AIに関する州法の10年間執行停止案」は、AIという急速に進化する技術に対して、各国がどのように向き合い、ルールを形成していくべきかという大きな問いを私たちに投げかけています。イノベーションを促進し国際競争力を維持したいという産業界の要請と、AIがもたらす様々なリスクから消費者を保護し、公正な社会を維持したいという市民社会の要請との間で、最適なバランス点を見出すことの難しさが改めて示されたと言えるでしょう。
この法案の今後の動向は、米国内だけでなく、グローバルなAI規制の議論にも影響を与える可能性があります。日本においても、AI技術の健全な発展と社会実装を推進するために、本稿で取り上げたような海外の事例を参考にしつつ、自国の状況に即した実効性のあるルール作りを進めていくことが重要です。